2016年~2018年の著作・制作物
※本学教職員の所属・職位は発行当時のものです。
『女子力革命』東京書籍(2018年)

萱野 稔人(総合政策学科教授) 著
結婚はどうする?子どもはほしい?仕事は何歳まで?老後のお金は?後戻りのできない超少子・超高齢時代。既存のモデルが通用しない時代を生きぬいていくために必要とされる「力」とは何か?津田塾大学の学生が、これから直面せざるをえないみずからの人生の問題を世に問う。
(東京書籍 1,400円+税)
『日本型組織の病を考える』角川新書(2018年)
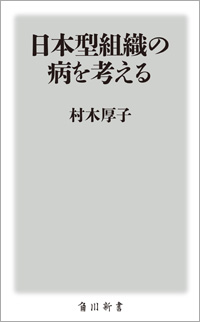
村木 厚子(総合政策学科客員教授) 著
公文書改竄、セクハラ、日大アメフト事件……繰り返す不祥事の本質とは? 冤罪のち厚生労働事務次官までを務めたからこそわかった「日本型組織の病」とは何か。硬直化を打破する「静かなる改革」までを語り尽くす。
(角川新書 840円+税)
『心理言語学を語る — ことばへの科学的アプローチ』誠信書房(2018年)

トレヴァー・ハーレイ 著/星野 徳子(英文学科准教授) 分担翻訳
私たちはどのように言語を習得し、理解し、使いこなしているのか。人間のみに可能なこの複雑なプロセスを、子どもの言語獲得、動物のコミュニケーション、失語症・失読症の研究、言葉の認知過程等、各側面から科学的アプローチを駆使して解き明かす。言語の心理学の主要なテーマについて網羅し、多様な議論を整理した、類を見ない優れた解説書。
原書名:Talking the Talk: Language, Psychology and Science 2nd Edition
※ 星野准教授は 第3章「子どもの言語獲得」と第8章「発話と失語症」を翻訳。
(誠信書房 5,200円+税)
『KOKORO』国書刊行会(2018年)
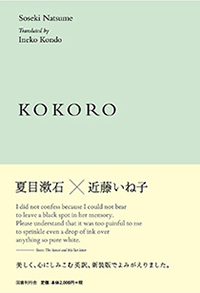
夏目 漱石著、近藤 いね子(英文学科名誉教授)訳
日本女性初の文学博士である、英文学科の近藤いね子名誉教授(1911年-2008年)が昭和16年に英訳した『KOKORO』が新装版として刊行されました。
開戦間近の昭和16年に刊行された近藤いね子英訳の夏目漱石作『こゝろ』。英文学者で評論家の渡部昇一氏絶賛の名訳が、いま、新装版としてよみがえる。渡部昇一氏「この人の英訳の『こゝろ』を読んで、私はすっかりのめり込んだ。英語がいいのである。声を出して読んでいると、『こゝろ』の主人公の心が自分にしみこんでくるような気がしたのであった」。英語圏の方々はもとより、日本で英文学や国文学を学ぶ方々等、英語訳での夏目漱石の世界に興味を持たれる読者におすすめしたい一冊です。
(国書刊行会 2,000円+税)
『中国、香港、台湾におけるリベラリズムの系譜』有志舎(2018年)

中村 元哉(国際関係学科教授) 著
現代中国を読み解く際、「民主か独裁か」という切り口のみで語られることが多い。しかし、実際の状況はもっと複雑であり、現代中国において「自由と権力」をめぐる議論は20世紀前半以来の長い歴史を持っていることを忘れてはならない。そして、何よりも中国・香港・台湾のトライアングル関係を無視しては、その思想状況を理解することは困難である。本書は、様々な現実の奥底に潜んでいる近現代中国の自由を求めるリベラリズム思想と運動の歴史を、多くの思想家とこれら地域のトライアングル関係の歴史を通して読み解き、中国への新しい見方を提示する。
(有志舎 2,600円+税)
『少女のための性の話』ミツイパブリッシング(2018年)

三砂 ちづる(国際関係学科教授) 著
生理なんて来なくていい? 誰とでも寝ていいの? 避妊はどうして必要?
恋愛、パートナー選び、妊娠、出産、生殖技術との向き合い方まで。国際母子保健の専門家であり、日本の伝統的な身体作法にも詳しい著者が次世代女子に贈る、ココロもカラダも女子力アップするための虎の巻エッセー。オトナ一歩手前の女の子とお母さんが一緒に読むにも最適の性教育本。
(ミツイパブリッシング 1,700円+税)
『憲政から見た現代中国』東京大学出版会(2018年)

中村 元哉(国際関係学科教授) 著
※2018年度津田塾大学特別研究費出版助成を受けました。
(東京大学出版会 6,800円+税)
『東アジアの高齢者ケア— 国・地域・家族のゆくえ』東信堂(2018年)

森川 美絵(総合政策学科教授)、須田木 綿子、平岡 公一 編著
日本・台湾・韓国の3か国は、高齢化社会への対応において、高齢者へのケアを家族に依存してきたことやサービスの財源に社会保険方式を採用することなど、福祉レジームにある程度の共通性がある。他方で、限られた資源を用いて急増する介護サービス需要にいかに対処するかが問われる中、それぞれの福祉レジームには様々な変化や固有の工夫もみられる。本書は、西洋とは異なる歴史や文脈を持つ東アジアの3か国を取り上げ、その展開を、国レベル、地方自治体レベル、各論という分析レベルを設定した上で、比較考察している。日本の今後の高齢者ケアのあり方にも重要な示唆を与える、時宜にかなった労作。
(東信堂 3,800円+税)
『先住民からみる現代世界 — わたしたちの〈あたりまえ〉に挑む』昭和堂(2018年)
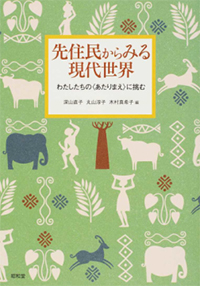
木村 真希子(国際関係学科准教授)、丸山 淳子(国際関係学科准教授)、深山 直子 編
アイヌやマオリなど「先住民」として権利を主張する人々。彼らは世界をどのように見ているのだろう?本書では、先住民を主体とする見方と、先住民という概念を切り口とする見方の双方を、フィールドワークをもとに描き出す。これまでとは違った世界が見えてくるかもしれない。
(昭和堂 2,500円+税)
『越境する歴史認識 — ヨーロッパにおける「公共史」の試み』岩波書店(2018年)
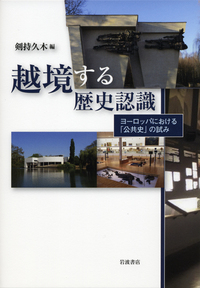
剣持 久木 編/吉岡 潤(国際関係学科教授) 分担執筆
「慰安婦」問題をはじめ、国内外で歴史認識をめぐる分断が絶え間なく生じ続けるなか、歴史学はどのように現実にコミットしうるのだろうか——ナチズムや戦争責任などをめぐり日本と同様の問題を抱えてきたヨーロッパで歴史認識の分断を越境するために積み重ねられてきた、博物館やテレビドラマなどの公共史の試みを紹介し、その可能性を探る。
※ 吉岡教授は 第4章「ポーランド現代史における被害と加害 — 歴史認識の収斂・乖離と歴史政策」を執筆。
(岩波書店 3,600円+税)
『被抑圧者の教育学 50周年記念版』亜紀書房(2018年)

パウロ・フレイレ 著/三砂 ちづる(国際関係学科教授) 訳
解放の教育学はこの本から始まった ——
教育の視点から「抑圧の文化」に対峙する視点を提示する。世界中で読み継がれている教育思想と実践の書であり、常に新しい読者を獲得してきた信頼の一冊。
1979年以来、版を重ねること13版。常に新しい読者を獲得してきた名著が読みやすい新訳で生き返る。
ポルトガル語版を訳して2011年1月に出版された「新訳・被抑圧者の教育学」に、出版50周年を記念してドナルド・マセドが寄せた長いまえがき、ノーム・チョムスキーらのインタビューを含めたあとがきを加えて、50周年記念版とした。あとがきの翻訳は松崎良美国際関係学科助教の協力を得ている。
(亜紀書房 2,600円+税)
『新版 五感を育てるおむつなし育児』主婦の友社(2018年)
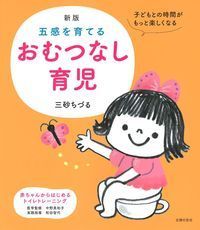
三砂 ちづる(国際関係学科教授) 著
赤ちゃんの機嫌がよくなり、ママは育児が楽になる、はじめ方のコツからイヤイヤ期の乗り切り方。幸せ育児法を伝えます。
(主婦の友社 1,300円+税)
『その後の震災後文学論』青土社(2018年)

木村 朗子(国際関係学科教授) 著
すぎゆく日常のなかで、わたしたちは、震災の何を記憶し、そして何を忘れてしまったのか——。あの日に更新することを余儀なくされた「読み」と「批評」と真摯に向き合い、これからの文学の地平を見通す。
(青土社 2,000円+税)
『もっと、海を — 想起のパサージュ』鳥影社(2018年)
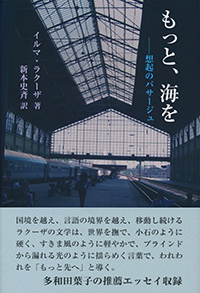
イルマ・ラクーザ 著/新本 史斉(国際関係学科教授) 訳(多和田葉子 あとがき)
「海は⻘で緑で碧⻘で鼠色で灰色で黒く、白くもあり薔薇色でもあり赤でもオレンジでも金でも銀でもあった。それは天空を映す鏡で、どの日もどこかしら 違っていた。凪ぐことも縮れることも波立つことも逆巻くこともあった。それはいかなる定義をも拒んでいた。その変容する力を、捉え難さを愛することをわたしは学んだ。」– 国境を越え、言語の境界を越えて移動し続ける翻訳者そして多言語作家、イルマ・ラクーザの自伝作品が日本語になりました。足裏できしむ小石のような、車窓から吹き込むすきま風のような、ブラインドから漏れる光のような彼女の言葉は、私たちがはじめて世界に触れた時の感覚を呼び起こしてくれます。
「言葉の夜行列車に乗って揺られていけば、それが海の波の揺れになり、遠い記憶の中のゆりかごの揺れになり、詩的陶酔となって、読者をどこまでも連れて行ってくれる。」(多和田葉子あとがきより)
(鳥影社 2,400円+税)
『トマス・ハーディの文学と二人の妻—「帝国」「階級」「ジェンダー」「宗教」を問う』音羽書房鶴見書店(2017年)
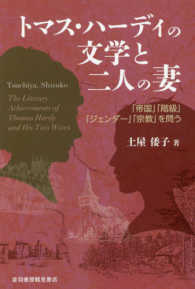
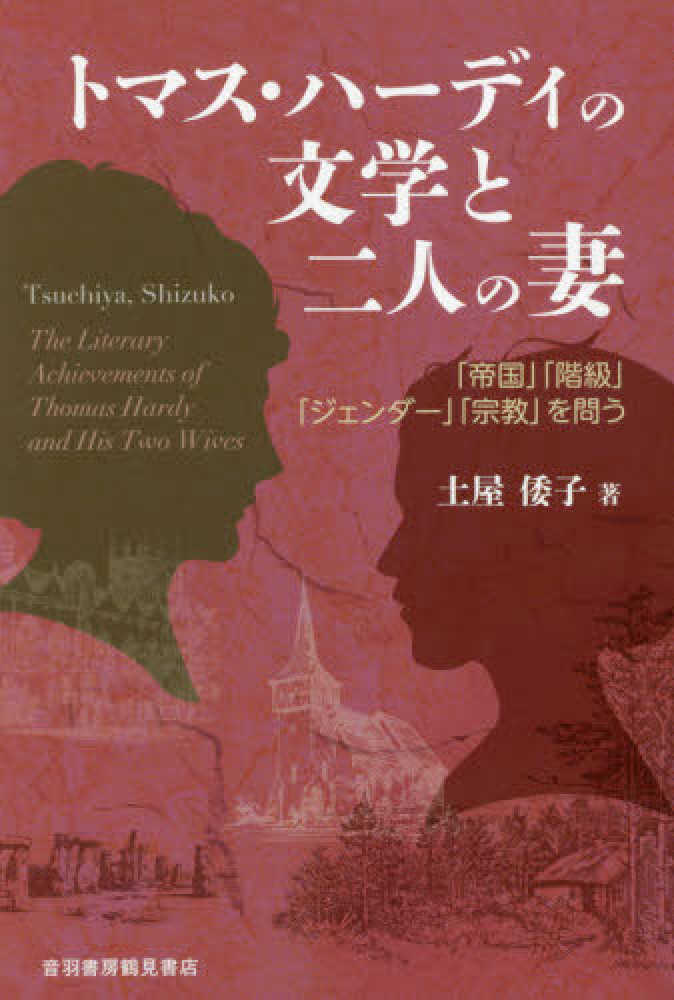
土屋 倭子 (津田塾大学名誉教授)著
(音羽書房鶴見書店 3,500円+税)





