第7回 学生スタッフレポート
乳幼児保育・教育から学ぶこと
今西 恵子 氏(東京学芸大こども未来研究所専門研究員、東京学芸大学芸の森保育園施設長・副園長)
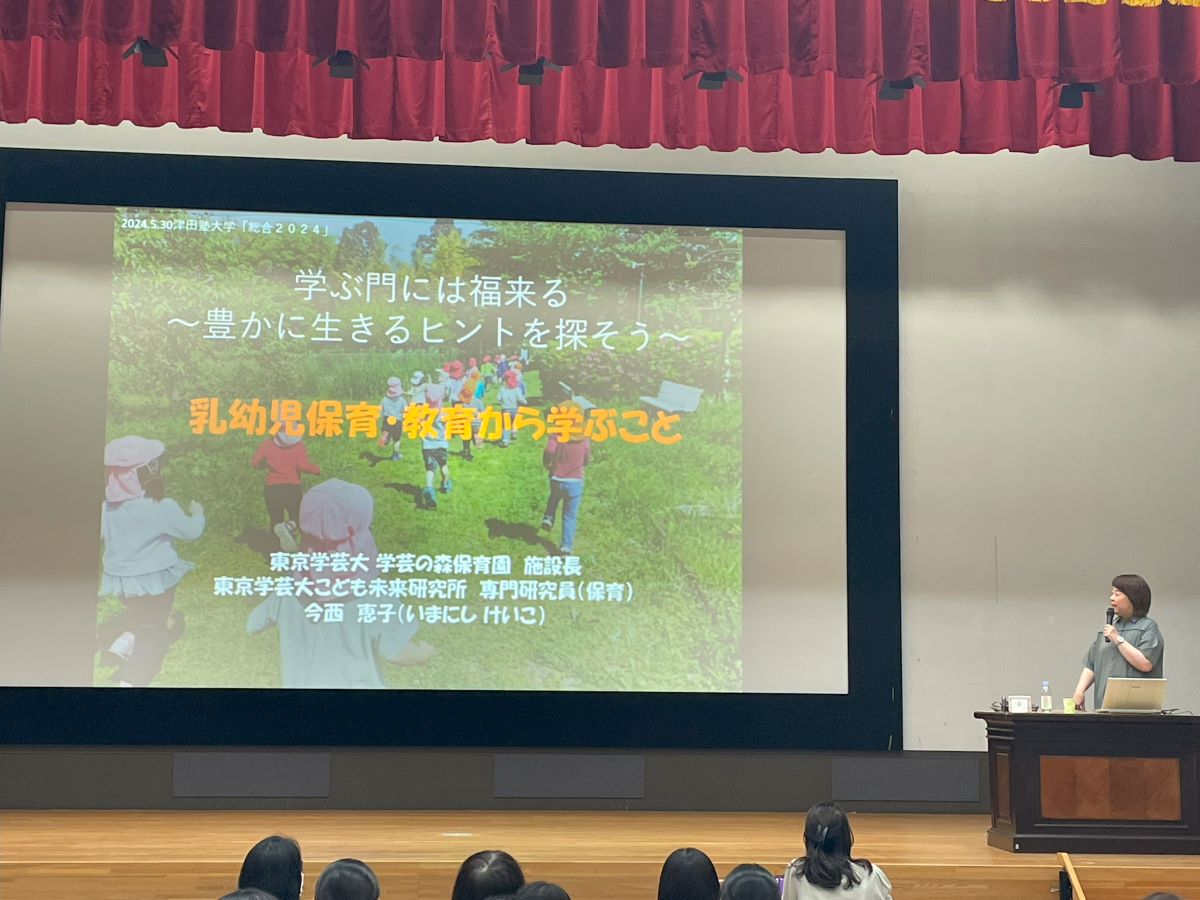
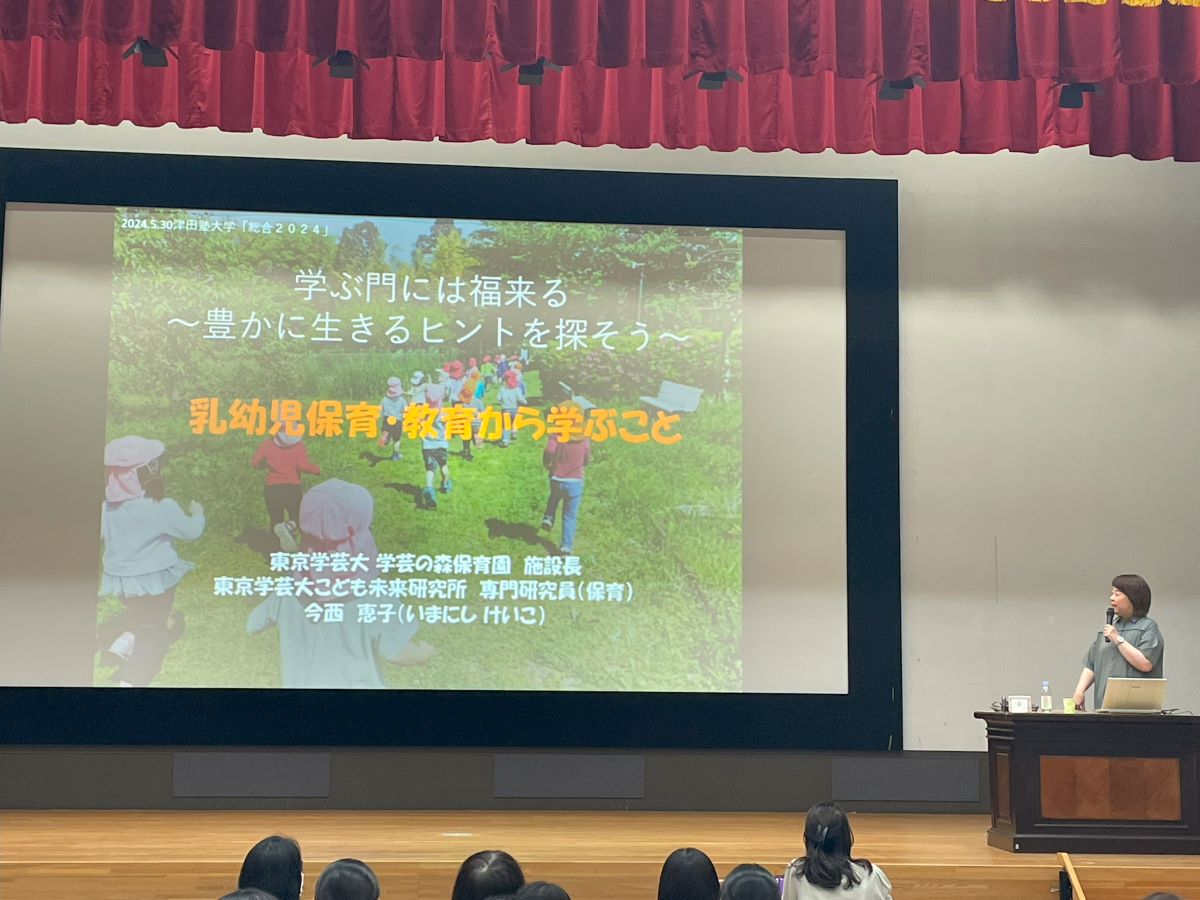
こんにちは!
「総合2024」第7回、5月30日(木)の講演は、東京学芸大こども未来研究所専門研究員を務めながら、東京学芸大学芸の森保育園施設長・副園長としても活躍されている、今西恵子さんにお越しいただきました。今回は「乳幼児保育・教育から学ぶこと」というテーマでのお話に加え、保育園で働きたいという夢を追いかけ、壁にぶつかりながらも、気づきを得て成長する「1人の人間」としての貴重なお話を伺うこともできました。
今回の講演は学びに関連するお話が多くあったため、その中から特に印象に残ったお話を3つ抜粋して紹介させていただきます。
1つ目は、「遊び」が子どもにとって一番の学びだというお話です。子どもは遊びを通して主体性や協調性を身に着けていくとともに、様々な人や自然と触れ合い、成長していくそうです。私たちは学びと聞くと、学校の授業を思い浮かべてしまいがちですが、実際は普段の生活から学ぶことの方が多いのではないでしょうか。電車に乗っているとほとんどの人がイヤホンをつけてスマートフォンを見ています。私もその1人ですが、結論づけられた情報の多いスマートフォンを見るよりも、ふと見た景色や耳に入ってくる世間話の方が想像力が働き、得るものが多いのではないか、だからこそもっと視野を広げてみるべきではないかと考えさせられました。また、保護者の方からどのように子どもの主体性を育てれば良いかというお悩みがよく寄せられるとお話くださいました。これに対して今西さんは、「子どもがやりたいことを何でもやらせてあげることが本当の主体性なのか」を自身に問い続け、「大人が見守りながら適切に働きかけてあげることで、本当の主体性が育てられるのではないか」という考えに辿りつかれたそうです。子どもの主体性が養われる時期に大人がここまで真剣に向き合っている事にとても驚くとともに、学びの原点である「遊び」の大切さを感じました。
2つ目は、Z世代の約5割が「子どもは好きだけれど、将来育てたいとは思わない」といった、子育てに関して消極的な考えを持っているというお話です。今西さんはこのような状況を改善するために、子ども・保護者・学生が参加するイベントを開催し、学生が子どもと触れ合いながら子育てについて考えたり、保護者から話を聞いたりする機会を設けていらっしゃいます。イベントを終えると、多くの学生から「参加してよかった」「やはり子育ては大変そうだが、楽しいことの方が多いと思った」という意見が寄せられるそうです。多くの若者が子育てに関して消極的なイメージを持っているのは、実際に体験したり、体験した人たちから話を聞いたりする機会があまりないからだと思います。そのことにいち早く気づいて、リアルタイムな課題に取り組むだけでなく、将来子育てをする立場になる若者のことも考えていらっしゃる今西さんのような方々の存在があるからこそ、その熱意が次の世代へと引き継がれているのだと感じました。子育てに限らず、自分が漠然と不安を感じていること、興味のあることは、自分から行動を起こして考えを深めていかなければならないとも思いました。
3つ目は、今西さんご自身の「学び」についてのお話です。今西さんは自分が興味を持ったところに行って、考える経験から新しいアイデアが生まれると仰っていました。最近では、「ゴッホの世界を五感で感じる没入型展覧会『ゴッホ・アライブ』」をSNSでみて興味を持ち、訪れたそうです。そしてそこに展示されていた影絵の作品をご覧になり、子どもたちの遊びになるかもしれないと思いついたとのことでした。私は興味があってもなかなか行動に移せなかったり、同じ作品を見ていても他の人より感情が湧いてこなかったりすることに悩んでいました。そんな悩みを抱えていただけに、「これってこれに活きるかも!」というような、別の観点から物事を眺めている今西さんの視点が私にとってはとても新鮮でした。「生きているうちは感じる体験をし続けたい。そういう人生は豊かだ思う」この言葉は今回の講演で一番印象に残っている言葉です。偏見にとらわれず、広い視野を持って、新しいことに挑戦することが、新たな「学び」を生み出すきっかけになるのではないかと思いました。
「総合2024」第7回、5月30日(木)の講演は、東京学芸大こども未来研究所専門研究員を務めながら、東京学芸大学芸の森保育園施設長・副園長としても活躍されている、今西恵子さんにお越しいただきました。今回は「乳幼児保育・教育から学ぶこと」というテーマでのお話に加え、保育園で働きたいという夢を追いかけ、壁にぶつかりながらも、気づきを得て成長する「1人の人間」としての貴重なお話を伺うこともできました。
今回の講演は学びに関連するお話が多くあったため、その中から特に印象に残ったお話を3つ抜粋して紹介させていただきます。
1つ目は、「遊び」が子どもにとって一番の学びだというお話です。子どもは遊びを通して主体性や協調性を身に着けていくとともに、様々な人や自然と触れ合い、成長していくそうです。私たちは学びと聞くと、学校の授業を思い浮かべてしまいがちですが、実際は普段の生活から学ぶことの方が多いのではないでしょうか。電車に乗っているとほとんどの人がイヤホンをつけてスマートフォンを見ています。私もその1人ですが、結論づけられた情報の多いスマートフォンを見るよりも、ふと見た景色や耳に入ってくる世間話の方が想像力が働き、得るものが多いのではないか、だからこそもっと視野を広げてみるべきではないかと考えさせられました。また、保護者の方からどのように子どもの主体性を育てれば良いかというお悩みがよく寄せられるとお話くださいました。これに対して今西さんは、「子どもがやりたいことを何でもやらせてあげることが本当の主体性なのか」を自身に問い続け、「大人が見守りながら適切に働きかけてあげることで、本当の主体性が育てられるのではないか」という考えに辿りつかれたそうです。子どもの主体性が養われる時期に大人がここまで真剣に向き合っている事にとても驚くとともに、学びの原点である「遊び」の大切さを感じました。
2つ目は、Z世代の約5割が「子どもは好きだけれど、将来育てたいとは思わない」といった、子育てに関して消極的な考えを持っているというお話です。今西さんはこのような状況を改善するために、子ども・保護者・学生が参加するイベントを開催し、学生が子どもと触れ合いながら子育てについて考えたり、保護者から話を聞いたりする機会を設けていらっしゃいます。イベントを終えると、多くの学生から「参加してよかった」「やはり子育ては大変そうだが、楽しいことの方が多いと思った」という意見が寄せられるそうです。多くの若者が子育てに関して消極的なイメージを持っているのは、実際に体験したり、体験した人たちから話を聞いたりする機会があまりないからだと思います。そのことにいち早く気づいて、リアルタイムな課題に取り組むだけでなく、将来子育てをする立場になる若者のことも考えていらっしゃる今西さんのような方々の存在があるからこそ、その熱意が次の世代へと引き継がれているのだと感じました。子育てに限らず、自分が漠然と不安を感じていること、興味のあることは、自分から行動を起こして考えを深めていかなければならないとも思いました。
3つ目は、今西さんご自身の「学び」についてのお話です。今西さんは自分が興味を持ったところに行って、考える経験から新しいアイデアが生まれると仰っていました。最近では、「ゴッホの世界を五感で感じる没入型展覧会『ゴッホ・アライブ』」をSNSでみて興味を持ち、訪れたそうです。そしてそこに展示されていた影絵の作品をご覧になり、子どもたちの遊びになるかもしれないと思いついたとのことでした。私は興味があってもなかなか行動に移せなかったり、同じ作品を見ていても他の人より感情が湧いてこなかったりすることに悩んでいました。そんな悩みを抱えていただけに、「これってこれに活きるかも!」というような、別の観点から物事を眺めている今西さんの視点が私にとってはとても新鮮でした。「生きているうちは感じる体験をし続けたい。そういう人生は豊かだ思う」この言葉は今回の講演で一番印象に残っている言葉です。偏見にとらわれず、広い視野を持って、新しいことに挑戦することが、新たな「学び」を生み出すきっかけになるのではないかと思いました。
国際関係学科1年 たらこそふと
コメントシートより
- 一斉保育と自由保育の対立の話が一番興味深いなと思った。人間の最大の強みは群れを作って集団で生きることであるため、子どもを集団の中で教育することが重要である。けれど、子どもはもちろん一人一人個性があるため、活動のスピードには幅がある。だからそれを認めてあげることが大切で、逆にそういった教育の中で子どもにも、周りと合わせる協調性の大切さを教えることが出来る。こういった意味で、「緩やか」な一斉教育は大事なのだなと思った。年々、自分事として考えるようになっている子育てについて、現場で実際に活動する講師の方のお話を聞くことが出来てよかった。
- 私はあまり“子供が欲しい”と思わない典型的なZ世代の学生です。しかし、今西さんのお話や映像を拝見しているうちに「子育てをすること」自体が人生にとってかけがえのない「学び」である、という考え方を知ることができました。 「私はまだ子育てについて全然知らないのかもしれない」と自分を見つめ直すきっかけになりました。子育ての社会制度について調べたりプログラムに参加したりすることで学びを得て、自分の将来や幸せについてゆっくり考えていきたいです。
- 子育てや出産を経験して、現場に戻ることを諦めていらした中でも、子育て支援に興味を向け、経験を積みたいと思って大学で勉強なさったと知り、素晴らしいと思った。保護者や子どもだけでなく大学生にも焦点を当てて、イベントの参加を依頼し、将来のキャリアやビジョンを持てるような活動をなさっていることも知りました。今だけでなく未来を見据えた教育活動に力を注いでいらっしゃるので、とても視野が広いと思った。また、「何気ない行動が話題になったり、子どもとの関わりなどに活きたりしているから、これからも「感じること」を続けていきたい」と仰っていらしたことに非常に共感した。私も総合以外の授業の内容や休日や過去に感じたことによって困っていたことを解決した経験がたくさんあったため、今後もどんどん外に出て、したことがない経験をしていきたいと思った。





