第24回 学生スタッフレポート
4000人の「若年ホームレス」がいる東京で「生きる権利」を守る
岩本 菜々 氏(NPO法人 POSSE理事・大学院生)
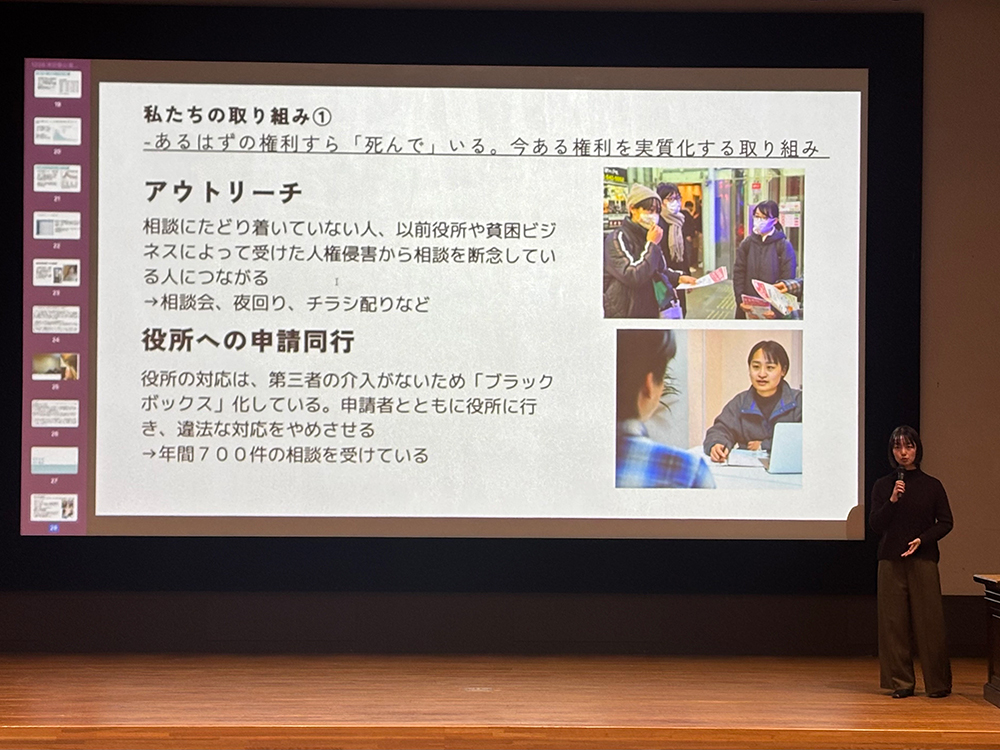
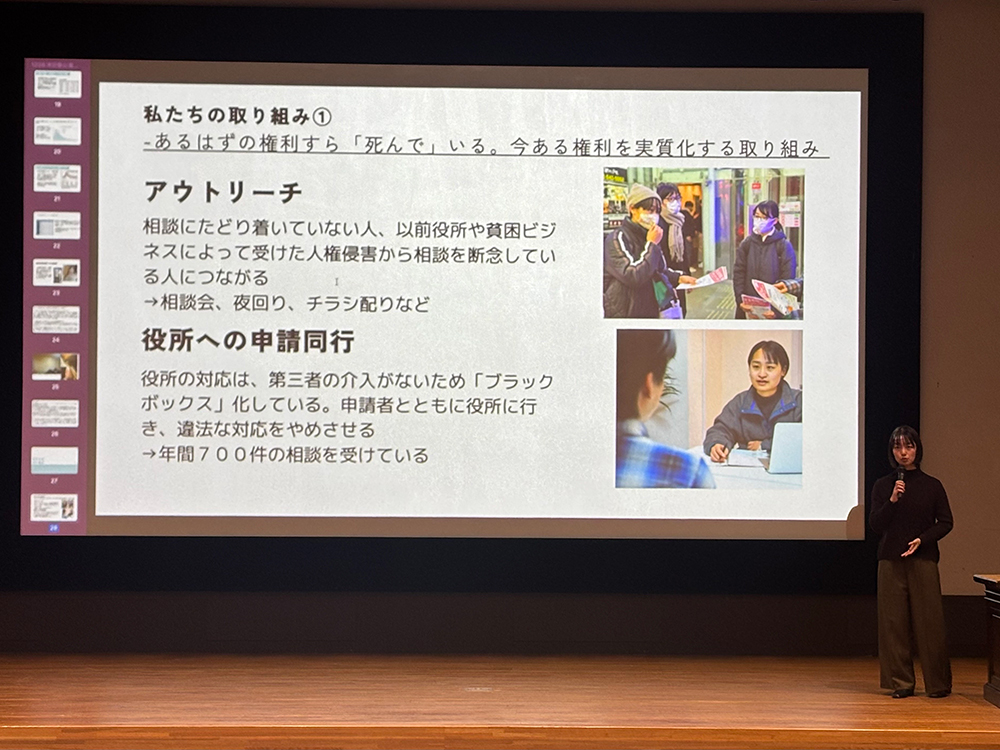
こんにちは!冬は寒さが厳しく体調を崩しがちな季節ですが、皆さんいかがお過ごしですか?クリスマスやお正月の時期には、街に素敵な装飾や美味しい食べ物が溢れるようになりますね。
12月26日の「総合2024」の講演は、NPO法人POSSEの理事で大学院生である岩本菜々さんにお越しいただき、身近に存在する日本社会での貧困問題について講演していただきました。物が溢れて豊かに見える日本ですが、貧困で命を落とす人もいます。その現状について、様々なデータをもとにお話くださいました。それらのデータによると、経済的困窮を理由とした自殺者、餓死者、凍死者などは毎年一定数存在しているのですが、そのことは不可視化されているそうです。岩本さんはその人たちの命を、「生活保護がきちんと機能していたり、インフラが止まったりすることがなければ失われることがなかった命」だと話されていました。
貧困の不可視化について、次のような例もあります。厚生労働省の調査によれば、ホームレスの数は減少しているのですが、岩本さんは調査の方法に問題があるのではないかと考えています。この調査は日中に屋外にいるホームレスの人を目視でカウントしているそうですが、ホームレスの人は日中は働いていたり、図書館などの屋内にいたりするケースが多いため、正確な状況を反映した調査結果とは言いにくいようです。また、ネットカフェで生活している人もカウントされません。
東京都の調査によると、ネットカフェで生活している人のうち、86%の人は仕事に就いているという現状が分かり、働いていても衣食住に困っている人が多いことが分かると思います。生活するのに最低限必要な費用(最低生計費)を稼ぐことができない人が34.3%もいて、普通に働いている人が貧困に陥り、命の危険に晒される現状があるということです。貧困問題を考えるにあたって、生きていけない程の低賃金や非正規雇用の問題を考える必要があることは明らかです。
それでは、生活保護などのセーフティーネットは正しく機能しているのでしょうか。その答えとして、多くの自治体では生活保護をなるべく申請させないように様々な理由をつけて申請を断るという水際作戦が行われているという事実があります。また、生活保護を受給できたとしても劣悪な住まいしか提供されないこともあるそうです。POSSEには、生活保護の申請を断られて相談に来る人が多くいます。岩本さんは福祉が正しく機能しない理由はコストカットであると指摘され、「行政が生存とお金を天秤にかけた結果、お金を取る」ことを問題視されていました。
こうした問題が山積する中でPOSSEは、相談にたどり着いていない人に繋がるためのチラシ配りなどのアウトリーチ活動や役所への申請同行などの活動をしています。「申請に同行する」という第三者の介入が、ブラックボックス化しがちな役所での対応に効果的だといいます。また、不可視化されたホームレスの数を明らかにする人口調査プロジェクトも行っています。今後は農地運営と食糧支援を組み合わせたプロジェクトの展開を考えているそうです。
質疑応答では、民間団体が貧困解決の役割を担い過ぎると行政の福祉が発展しないのではないかという質問が寄せられました。確かに、本来行政でやるべきことを民間が肩代わりせざるを得なくなることは問題ですが、福祉制度の歴史は地域の互助の精神を制度化するために生まれました。「民間の働きを示すことで行政へ圧力が生まれる」と考えると良いのではないかとお答えくださいました。
私自身、福祉が正しく機能していないのではないかと感じることが多いです。命に関わる問題をコストカットして処理してしまうことにも疑問を感じています。低賃金が続けば、貧困に苦しむ人は増え、国としても持続可能な状態にならないと思います。岩本さんの講演から、第三者による監視の大切さを学びました。福祉が機能不全に陥らないためにも、私たち一人一人が問題に関心を持つことも大切だと考えます。
貧困問題にこれまで関心があった人もなかった人も、今回の講演を聞いて新たな学びがあったのではないでしょうか。社会問題を考える中で自分なりの考えを持つことができますが、それはかけがえのない財産であり学びであると私は思います。
12月26日の「総合2024」の講演は、NPO法人POSSEの理事で大学院生である岩本菜々さんにお越しいただき、身近に存在する日本社会での貧困問題について講演していただきました。物が溢れて豊かに見える日本ですが、貧困で命を落とす人もいます。その現状について、様々なデータをもとにお話くださいました。それらのデータによると、経済的困窮を理由とした自殺者、餓死者、凍死者などは毎年一定数存在しているのですが、そのことは不可視化されているそうです。岩本さんはその人たちの命を、「生活保護がきちんと機能していたり、インフラが止まったりすることがなければ失われることがなかった命」だと話されていました。
貧困の不可視化について、次のような例もあります。厚生労働省の調査によれば、ホームレスの数は減少しているのですが、岩本さんは調査の方法に問題があるのではないかと考えています。この調査は日中に屋外にいるホームレスの人を目視でカウントしているそうですが、ホームレスの人は日中は働いていたり、図書館などの屋内にいたりするケースが多いため、正確な状況を反映した調査結果とは言いにくいようです。また、ネットカフェで生活している人もカウントされません。
東京都の調査によると、ネットカフェで生活している人のうち、86%の人は仕事に就いているという現状が分かり、働いていても衣食住に困っている人が多いことが分かると思います。生活するのに最低限必要な費用(最低生計費)を稼ぐことができない人が34.3%もいて、普通に働いている人が貧困に陥り、命の危険に晒される現状があるということです。貧困問題を考えるにあたって、生きていけない程の低賃金や非正規雇用の問題を考える必要があることは明らかです。
それでは、生活保護などのセーフティーネットは正しく機能しているのでしょうか。その答えとして、多くの自治体では生活保護をなるべく申請させないように様々な理由をつけて申請を断るという水際作戦が行われているという事実があります。また、生活保護を受給できたとしても劣悪な住まいしか提供されないこともあるそうです。POSSEには、生活保護の申請を断られて相談に来る人が多くいます。岩本さんは福祉が正しく機能しない理由はコストカットであると指摘され、「行政が生存とお金を天秤にかけた結果、お金を取る」ことを問題視されていました。
こうした問題が山積する中でPOSSEは、相談にたどり着いていない人に繋がるためのチラシ配りなどのアウトリーチ活動や役所への申請同行などの活動をしています。「申請に同行する」という第三者の介入が、ブラックボックス化しがちな役所での対応に効果的だといいます。また、不可視化されたホームレスの数を明らかにする人口調査プロジェクトも行っています。今後は農地運営と食糧支援を組み合わせたプロジェクトの展開を考えているそうです。
質疑応答では、民間団体が貧困解決の役割を担い過ぎると行政の福祉が発展しないのではないかという質問が寄せられました。確かに、本来行政でやるべきことを民間が肩代わりせざるを得なくなることは問題ですが、福祉制度の歴史は地域の互助の精神を制度化するために生まれました。「民間の働きを示すことで行政へ圧力が生まれる」と考えると良いのではないかとお答えくださいました。
私自身、福祉が正しく機能していないのではないかと感じることが多いです。命に関わる問題をコストカットして処理してしまうことにも疑問を感じています。低賃金が続けば、貧困に苦しむ人は増え、国としても持続可能な状態にならないと思います。岩本さんの講演から、第三者による監視の大切さを学びました。福祉が機能不全に陥らないためにも、私たち一人一人が問題に関心を持つことも大切だと考えます。
貧困問題にこれまで関心があった人もなかった人も、今回の講演を聞いて新たな学びがあったのではないでしょうか。社会問題を考える中で自分なりの考えを持つことができますが、それはかけがえのない財産であり学びであると私は思います。
国際関係学科4年 シンシン
コメントシートより
- 以前にホームレスの人は減ってきているというニュースを見たのでそうなのかと思っていたのですが、今回の講義で「見えない貧困」に陥っている人がたくさんいることを知って驚きました。私はあまり貧困について興味がなかったのでなんとなくでニュースを見ていましたが、そのニュースの裏側にはもっと悲惨な現実が隠れていると言うことに気づくこともできました。貧困だけでなく、世の中のいろいろなことに現実が隠されていることがあると思うので、もっと物事を深く知ることを心がけて行こうと思いました。
- 平和な日本だと思っていたのに、思っていたより凍死者や餓死者が多くてびっくりした。私たちはそこから目を背けて、または知ろうとせずに現実味のないものとして遠ざけていたと思った。私も同じ国に住むものとして当事者意識を持ちたいと思った。そのために、自分にできることを考え行動してみたいと思った。また、生活保護のような福祉を強化して犯罪や居場所のない人を無くして欲しいと思った。
- 知っている人がいるだけでは社会は変わらない、知る・教える・学ぶの一歩先である「身体を動かしてみる」ことを蓄積していくことによって社会は変えていけるのだという言葉が印象的であった。「路上生活をされている方と接する際に、一緒に戦うという姿勢を持つことが重要である」という言葉からも感じられるように、彼女の淡々とした静寂な雰囲気の中にある力強さは、確かな経験と知識によるのだろうと感じた。路上生活を送る方々に対する社会保障というのは、国家によるもの故にコストという視点が設けられてしまう。路上生活を送る人々にとって、彼女の存在というのは、家族や政府よりも心強い存在なのではないかと感じた。人を守る上で心からの愛や優しさ以上に重要な存在は無いのだろうと考えていた。しかしながら、今回の講義を受けて、知識や経験を積み、活用していくことによって初めて人を守ることが出来るのだと感じた。考えることというのは誰でもできる。行動し成し遂げて初めて、特別な存在になれるのだと思い直した。





