第21回 学生スタッフレポート
アイヌを知り自分を知るー文化から社会まで
北原モコットゥナㇱ 氏(北海道大学アイヌ・先住民研究センター教授)
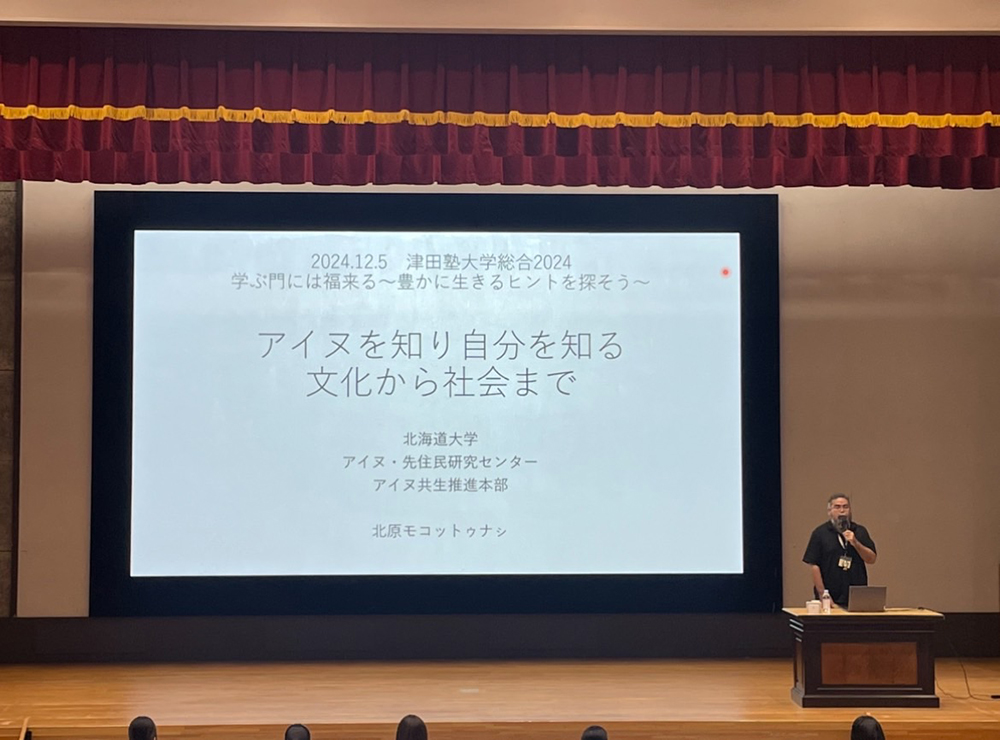
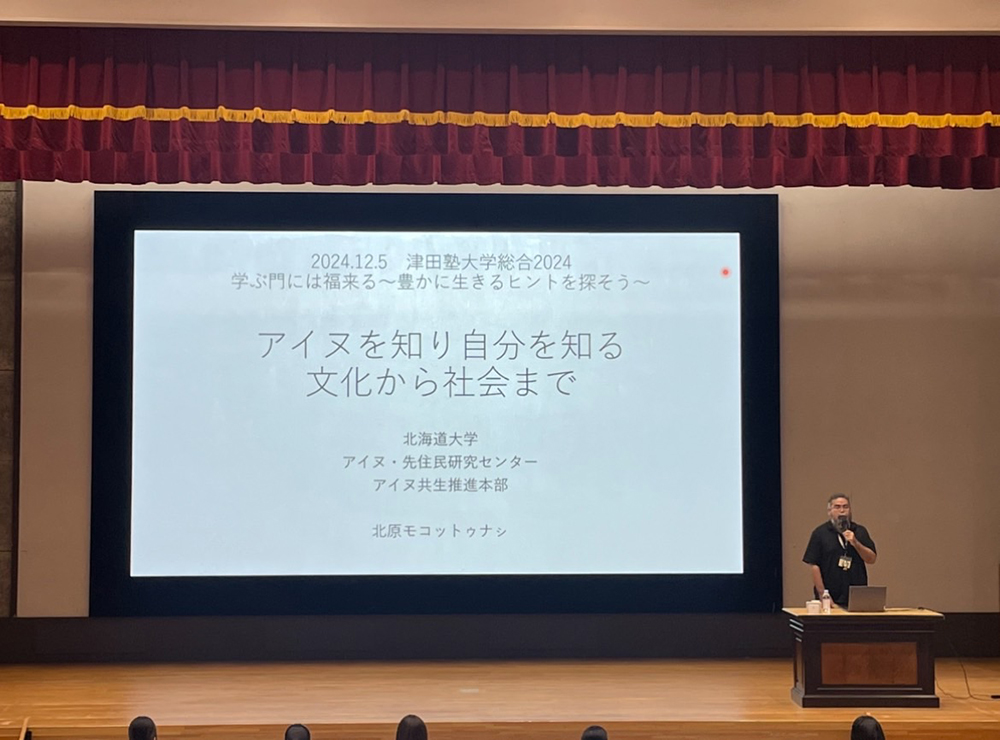
こんにちは!
「総合2024」第21回、12月5日(木)の講演は、北海道大学アイヌ・先住民研究センター教授を務められている、北原モコットゥナㇱさんにお越しいただき、「アイヌを知り自分を知るー文化から社会まで」というテーマでお話いただきました。
講演の最初にウポポ(アイヌの歌)でウコウㇰ(輪唱の様に旋律を少しずつずらして歌い継ぐ)を体験しました。初めて歌う歌で輪唱することは難しかったですが、会場が盛り上がって、暖かい雰囲気になりました。アイヌの文化を会場の全員で体験できてすごく貴重な経験になりました。
今回の講演で特に印象的だったことは2点あります。
1つ目は、文化の連続性についてのお話です。アイヌ民族の伝統的な服装として、木の皮で作られている、樹皮衣というものがあります。アイヌ民族ではない「和人」は、樹皮衣を見た際に自分の文化とは全く違うものと捉えてしまいがちです。しかし、日本や韓国、樺太でも似たような服を着ていたことがわかっています。自分とは違う文化に触れる時に相違点に目を向けがちですが、共通点に目を向けてみると自分と違う文化とのつながりを感じることができます。これは、異文化理解において大切な視点だと思いました。特に文化は近隣のものが伝わっていくことが多いので、和人文化とアイヌ文化は近い部分もあると知りました。
2つ目は社会の課題についてです。特に社会のマイノリティとマジョリティに焦点を当ててお話ししてくださいました。マイノリティはマジョリティの文化に合わせることを強制されてしまいます。例えば、アイヌ民族は日本で暮らす時に日本語を覚えないと生活できません。学校のカリキュラムも和人であることを前提として設計されています。また、アイヌ語を話すことを禁止されていた時期もありました。そのような歴史のせいで、アイヌ語を話せる人はごく少数になってしまっています。強制的にマジョリティに迎合させられてしまっています。マジョリティがマイノリティの文化を衰退させている点が恐ろしいと思いました。
自分がマイノリティなのかマジョリティなのかということは、性別から見る時や、民族から見る時などの視点によって変化します。マジョリティはマイノリティに肩身の狭い思いをさせている可能性が高いことを学びました。自らがいまどちらにいるのかを自覚して、マイノリティの人もありのままに生きることができるようにするためにはどう行動するべきか、どのような態度を避けた方が良いのかを考える必要があります。また、自分のマイノリティ性やマジョリティ性をまずは自覚しないといけません。マジョリティに属していれば当たり前だと思っている習慣や行動も多くあります。しかし、そのような状況に対して悲鳴をあげている人が存在しているかもしれません。また、マイノリティが見えなくされているという社会では民族間の憎悪を生み、それは何世代にも渡って受け継がれます。これでは、平和な世の中は実現しません。
今回の講演では、すべての人が平和に暮らしていくために、マイノリティへの配慮は大切だと考えさせられました。自分とは違う立場の人と話したり、その人たちについて考えることで、今までとは異なった新しい視点にも気がつくことができるので、私たちの視野を広げてくれると思います。自分がマジョリティだと自覚し、今までの行動がマイノリティを傷つけてしまっていたとしても自分を卑下する必要はないと北原さんは仰っていました。むしろ、行動と人格を分けることで自分の行動を見直すときの精神的負荷がなくなり、行動を改善しやすくなるそうです。しかし、差別は思いやりだけでは解決しません。社会制度や「常識」自体が差別的なこともあります。今までの差別の歴史を知って、知識を持ち、社会制度を変えていくことは、マイノリティもマジョリティも暮らしやすい社会にしていくために大切です。また、差別を目の当たりにした際に、どう行動するか日頃から考えていくことも重要だと思います。
「総合2024」第21回、12月5日(木)の講演は、北海道大学アイヌ・先住民研究センター教授を務められている、北原モコットゥナㇱさんにお越しいただき、「アイヌを知り自分を知るー文化から社会まで」というテーマでお話いただきました。
講演の最初にウポポ(アイヌの歌)でウコウㇰ(輪唱の様に旋律を少しずつずらして歌い継ぐ)を体験しました。初めて歌う歌で輪唱することは難しかったですが、会場が盛り上がって、暖かい雰囲気になりました。アイヌの文化を会場の全員で体験できてすごく貴重な経験になりました。
今回の講演で特に印象的だったことは2点あります。
1つ目は、文化の連続性についてのお話です。アイヌ民族の伝統的な服装として、木の皮で作られている、樹皮衣というものがあります。アイヌ民族ではない「和人」は、樹皮衣を見た際に自分の文化とは全く違うものと捉えてしまいがちです。しかし、日本や韓国、樺太でも似たような服を着ていたことがわかっています。自分とは違う文化に触れる時に相違点に目を向けがちですが、共通点に目を向けてみると自分と違う文化とのつながりを感じることができます。これは、異文化理解において大切な視点だと思いました。特に文化は近隣のものが伝わっていくことが多いので、和人文化とアイヌ文化は近い部分もあると知りました。
2つ目は社会の課題についてです。特に社会のマイノリティとマジョリティに焦点を当ててお話ししてくださいました。マイノリティはマジョリティの文化に合わせることを強制されてしまいます。例えば、アイヌ民族は日本で暮らす時に日本語を覚えないと生活できません。学校のカリキュラムも和人であることを前提として設計されています。また、アイヌ語を話すことを禁止されていた時期もありました。そのような歴史のせいで、アイヌ語を話せる人はごく少数になってしまっています。強制的にマジョリティに迎合させられてしまっています。マジョリティがマイノリティの文化を衰退させている点が恐ろしいと思いました。
自分がマイノリティなのかマジョリティなのかということは、性別から見る時や、民族から見る時などの視点によって変化します。マジョリティはマイノリティに肩身の狭い思いをさせている可能性が高いことを学びました。自らがいまどちらにいるのかを自覚して、マイノリティの人もありのままに生きることができるようにするためにはどう行動するべきか、どのような態度を避けた方が良いのかを考える必要があります。また、自分のマイノリティ性やマジョリティ性をまずは自覚しないといけません。マジョリティに属していれば当たり前だと思っている習慣や行動も多くあります。しかし、そのような状況に対して悲鳴をあげている人が存在しているかもしれません。また、マイノリティが見えなくされているという社会では民族間の憎悪を生み、それは何世代にも渡って受け継がれます。これでは、平和な世の中は実現しません。
今回の講演では、すべての人が平和に暮らしていくために、マイノリティへの配慮は大切だと考えさせられました。自分とは違う立場の人と話したり、その人たちについて考えることで、今までとは異なった新しい視点にも気がつくことができるので、私たちの視野を広げてくれると思います。自分がマジョリティだと自覚し、今までの行動がマイノリティを傷つけてしまっていたとしても自分を卑下する必要はないと北原さんは仰っていました。むしろ、行動と人格を分けることで自分の行動を見直すときの精神的負荷がなくなり、行動を改善しやすくなるそうです。しかし、差別は思いやりだけでは解決しません。社会制度や「常識」自体が差別的なこともあります。今までの差別の歴史を知って、知識を持ち、社会制度を変えていくことは、マイノリティもマジョリティも暮らしやすい社会にしていくために大切です。また、差別を目の当たりにした際に、どう行動するか日頃から考えていくことも重要だと思います。
英語英文学科学科1年 こむぎ
コメントシートより
- マジョリティ性が高いほど自分がマジョリティであることやそれによって窮屈を感じるマイノリティに気づかないという内容を聞いて納得したとともに自分が当たり前だと感じていることほど慎重に考えていく必要があると感じました。また区別、差別についての話がありましたが、誰も必要ととらえる区別はそんなに難しくないが、ある人にとっては便利な区別でも、ある人にとっては差別と捉えられるようなものになってしまうものが難しそうだと感じました。この正解のない問いについて考えることを放棄してはいけないと感じました。
- 今回の講演を聞いて、アイヌ民族に関する様々な問題は過去のものではなく現在進行形のものであることを学びました。そして、私たちは想像以上に無意識的にマイノリティに対する差別の中心におり、”知らないこと”自体がある意味差別的であることに気づきました。今までどこか他人事として捉えていたアイヌ民族について、ここにはいない誰かではなく、ともに生きる隣人について理解するために学ぶのだと考え、より深く勉強したいと思っています。





