第18回 学生スタッフレポート
不登校から生まれたもの
長村 知愛 氏(認定NPO法人ASOVIVA 代表理事)
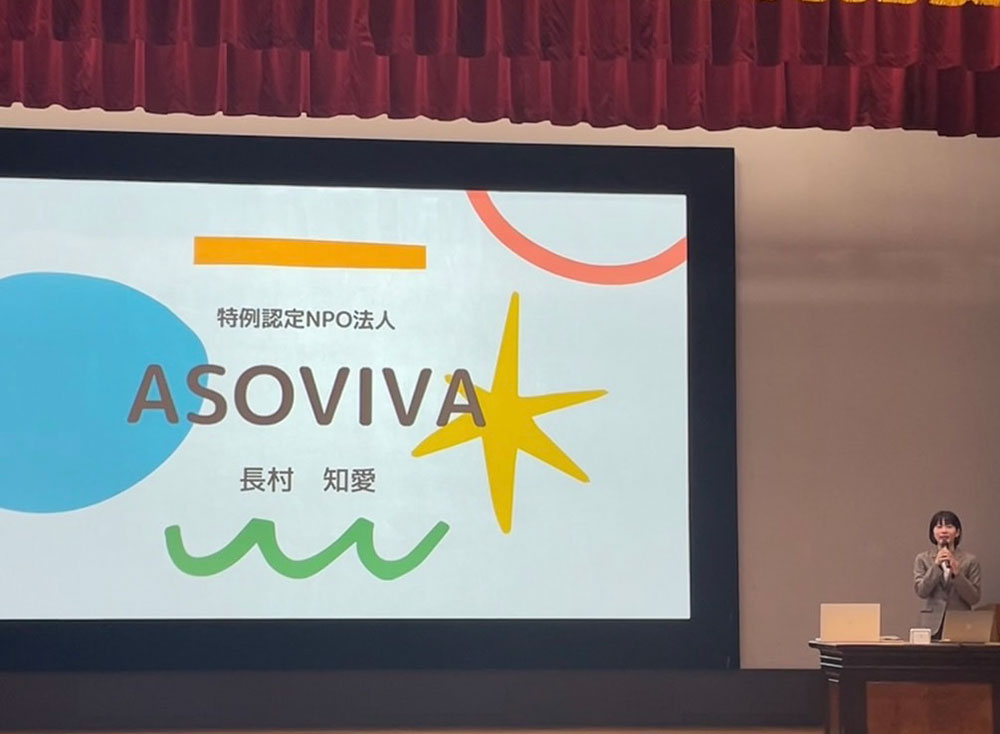
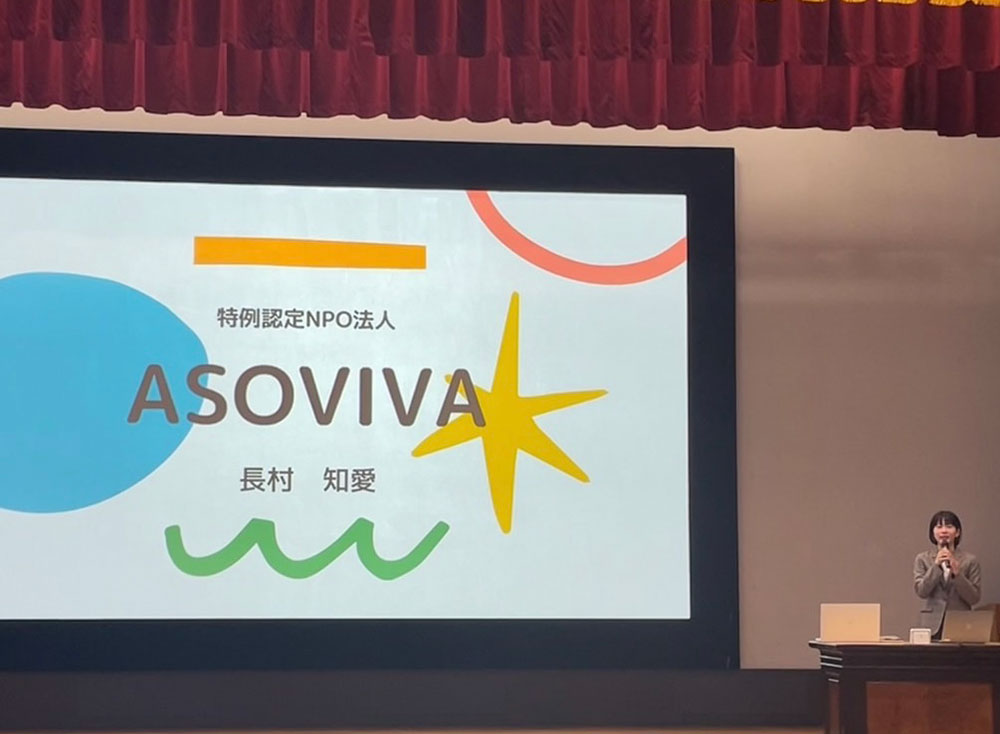
こんにちは!
「総合2024」第18回、11月7日(木)の講演は、認定NPO法人ASOVIVAで代表理事を務められている、長村知愛さんにお越しいただき、「不登校から生まれたもの」というテーマでお話を伺いました。
長村さんは、学校生活で「先生に怒られないようにちゃんとしなきゃ」「先生はどうしてほしいかな」と考えるうちに、自分の気持ちや行動を隠す傾向になってしまったそうです。そして、11歳で学校に行かないという選択をされました。一方で、「みんな当たり前のように学校行ってるのに、自分は行けていない。私の人生は詰んでしまったのか?」と考えることもあったのだそうです。しかし長村さんのお母様は、長村さんが学校に行かないという選択をとったことをご否定なさいませんでした。そこで長村さんは、「学校に行けないことを否定された子って、元気になれないのかな?」「否定された子は、どうなってしまうのだろう」と思い、お母様と共に子どもの居場所づくりを始められました。15歳の春にNPO法人ASOVIVAを設立し、代表理事に就任され、現在は子どもたちが社会的な自立に向かうためのスクールである「デモクラティックスクール ASOVIVA!」(以下ASOVIVA)を築100年の古民家を使って運営されています。
講演では長村さんの考える学びについて、子どもたちとのエピソードを交えながらお話しいただきました。さまざまな子どもが学びを通して生きる力を身につけることが伝わってきました。今回のスタッフレポートでは、「不登校だった頃のお母様からのサポート」と「ASOVIVAの存在意義」にフォーカスしてみたいと思います。
お母様から長村さんへのサポートの背景には「アドラー心理学」というものがあったそうです。その中でも「承認の言葉がけ」、「受け止め」、「問いかけ」の3つについてお話を伺いました。1つ目は、「承認の言葉がけ」。ここで気をつけるべきは「褒めてはいけない」ということです。その理由は「“褒められない私はダメ”という考えを防ぐため」だそうです。2つ目は、「受け止め」。「こんな私でもいい」と自分を受け入れることで自分を安心させることができ、自己肯定感を高めることにも繋がります。他責とは違うのですが、何かのせいにするということは立派な「受け入れ」です。例えば、相手がいる状況で物事がうまくいかなかった時、「あの人は今たまたま怒ってたんだろうな、タイミングが悪かったんだろうな」と受け入れるのです。また、欠点は自分に欠かせない部分であるとして受け入れます。そうすれば気持ちと行動を分けて考えられるようになるのです。3つ目は、「問いかけ」。「問いかけ」は「認知の歪み」と関連しています。「認知の歪み」とは自分の思考がネガティブに偏りすぎた結果生じます。そこで、ネガティブでない別視点から捉えることで、ネガティブに偏らないようにしてみるのです。「自分はどうしてそう感じているんだろう?」と何回も同じところで引っかかって問いかけを繰り返すことで、自分のことが分かるようになるとのことでした。これら3つの共通点は、全て自分にもしてあげられるという点です。これは不登校時代の長村さんがお母様にしてもらったことであり、こうしたサポートの下でも元気になるまで2年かかったそうです。「サポートをしてもらえない子はどうなってしまうのだろう」という疑問がASOVIVA設立の動機となったのでした。
こうして設立されたASOVIVAの存在意義とは何でしょうか。興味深かった取り組みは「ネガティブな経験も、経験させる」というものです。ASOVIVAでは豊かな経験を通して、「自分の人生を決めるのは自分であり、誰のせいにもできない」という考え方を小さい頃から持たせることで子どもたちの主体性を育んでいます。主体性を重んじる中で注意していることは子どもたちへの声のかけ方です。「主体的に考えましょう」という言葉がけ自体が、主体性を失わせてしまうとのこと。質疑応答の際、高校受験生の話が例に挙がりました。「アルバイト先の塾に受験生がいるけれど、その中にはなかなか勉強に身が入らない子もいる。この時期(11月)は気合いを入れるべきだと思うが、主体性を重んじるならばどのような声かけをするべきか」との質問です。長村さんの答えでは、「自分で自分のスイッチを入れるのが大切で、できてもできなくても、それは1つの学び。自分のことは自分でするしかないと伝えなければならない。自分の置かれている状況は自分で判断しなければならない。頑張ると決めたのであればサポートする。現実を教えることも大切」とのことでした。人生における判断を子どもにさせ、その答えは決まっていないことが多いため、自力で出した答えは自分の学びに繋がっていくということです。「自分で考え、自分の答えを見つける」これがASOVIVAで子どもたちが得る主体性の重んじられた学びなのです。自分で自分の人生を決めるという価値観を育てることは、型にハマったやり方ではない人生選択を可能にします。これこそASOVIVAの存在意義なのではないでしょうか。
最後に、今回の講演を聞いて私が感じたことを紹介します。それは、学校のやり方や大勢の中に染まっている自分に対して疑問を持つことは成長への第一歩だということです。疑問を持つことが、これから自分の人生で何をしたいのかを考える原動力になっていると感じました。自分で自分の人生を決めるという価値観を育てることは意義深いことで、周囲とは違った独自の人生選択ができるようになると思います。これが社会にもっと受け入れられれば、多くの人が自分の生き方にゆとりが持てるようになるのではないでしょうか。私には、長村さんの「人生は螺旋状に成長していて、上に向かって成長している」という考え方がとても印象的でした。最短ルートを通らなくても、疑問に思って考えて自分なりの答えを見つけ出す複雑なプロセスこそが「学び」であるということだと思います。普段忙しなく生きていると最短ルートを通ろうとして疑問を持つこと自体忘れてしまいがちです。それでも立ち止まって疑問を持って視野を広げてみたら、小さな学びも見つけることができるかもしれません。大人であろうと子どもであろうと、余裕を持って生きることの大切さは変わらないのです。こうして、身の回りにある環境に感謝したり、そこに落ちている学び、小さな喜びに気づいたりできることで自分の人生は「学び」を通して一層豊かになっていくのだと思います。
「総合2024」第18回、11月7日(木)の講演は、認定NPO法人ASOVIVAで代表理事を務められている、長村知愛さんにお越しいただき、「不登校から生まれたもの」というテーマでお話を伺いました。
長村さんは、学校生活で「先生に怒られないようにちゃんとしなきゃ」「先生はどうしてほしいかな」と考えるうちに、自分の気持ちや行動を隠す傾向になってしまったそうです。そして、11歳で学校に行かないという選択をされました。一方で、「みんな当たり前のように学校行ってるのに、自分は行けていない。私の人生は詰んでしまったのか?」と考えることもあったのだそうです。しかし長村さんのお母様は、長村さんが学校に行かないという選択をとったことをご否定なさいませんでした。そこで長村さんは、「学校に行けないことを否定された子って、元気になれないのかな?」「否定された子は、どうなってしまうのだろう」と思い、お母様と共に子どもの居場所づくりを始められました。15歳の春にNPO法人ASOVIVAを設立し、代表理事に就任され、現在は子どもたちが社会的な自立に向かうためのスクールである「デモクラティックスクール ASOVIVA!」(以下ASOVIVA)を築100年の古民家を使って運営されています。
講演では長村さんの考える学びについて、子どもたちとのエピソードを交えながらお話しいただきました。さまざまな子どもが学びを通して生きる力を身につけることが伝わってきました。今回のスタッフレポートでは、「不登校だった頃のお母様からのサポート」と「ASOVIVAの存在意義」にフォーカスしてみたいと思います。
お母様から長村さんへのサポートの背景には「アドラー心理学」というものがあったそうです。その中でも「承認の言葉がけ」、「受け止め」、「問いかけ」の3つについてお話を伺いました。1つ目は、「承認の言葉がけ」。ここで気をつけるべきは「褒めてはいけない」ということです。その理由は「“褒められない私はダメ”という考えを防ぐため」だそうです。2つ目は、「受け止め」。「こんな私でもいい」と自分を受け入れることで自分を安心させることができ、自己肯定感を高めることにも繋がります。他責とは違うのですが、何かのせいにするということは立派な「受け入れ」です。例えば、相手がいる状況で物事がうまくいかなかった時、「あの人は今たまたま怒ってたんだろうな、タイミングが悪かったんだろうな」と受け入れるのです。また、欠点は自分に欠かせない部分であるとして受け入れます。そうすれば気持ちと行動を分けて考えられるようになるのです。3つ目は、「問いかけ」。「問いかけ」は「認知の歪み」と関連しています。「認知の歪み」とは自分の思考がネガティブに偏りすぎた結果生じます。そこで、ネガティブでない別視点から捉えることで、ネガティブに偏らないようにしてみるのです。「自分はどうしてそう感じているんだろう?」と何回も同じところで引っかかって問いかけを繰り返すことで、自分のことが分かるようになるとのことでした。これら3つの共通点は、全て自分にもしてあげられるという点です。これは不登校時代の長村さんがお母様にしてもらったことであり、こうしたサポートの下でも元気になるまで2年かかったそうです。「サポートをしてもらえない子はどうなってしまうのだろう」という疑問がASOVIVA設立の動機となったのでした。
こうして設立されたASOVIVAの存在意義とは何でしょうか。興味深かった取り組みは「ネガティブな経験も、経験させる」というものです。ASOVIVAでは豊かな経験を通して、「自分の人生を決めるのは自分であり、誰のせいにもできない」という考え方を小さい頃から持たせることで子どもたちの主体性を育んでいます。主体性を重んじる中で注意していることは子どもたちへの声のかけ方です。「主体的に考えましょう」という言葉がけ自体が、主体性を失わせてしまうとのこと。質疑応答の際、高校受験生の話が例に挙がりました。「アルバイト先の塾に受験生がいるけれど、その中にはなかなか勉強に身が入らない子もいる。この時期(11月)は気合いを入れるべきだと思うが、主体性を重んじるならばどのような声かけをするべきか」との質問です。長村さんの答えでは、「自分で自分のスイッチを入れるのが大切で、できてもできなくても、それは1つの学び。自分のことは自分でするしかないと伝えなければならない。自分の置かれている状況は自分で判断しなければならない。頑張ると決めたのであればサポートする。現実を教えることも大切」とのことでした。人生における判断を子どもにさせ、その答えは決まっていないことが多いため、自力で出した答えは自分の学びに繋がっていくということです。「自分で考え、自分の答えを見つける」これがASOVIVAで子どもたちが得る主体性の重んじられた学びなのです。自分で自分の人生を決めるという価値観を育てることは、型にハマったやり方ではない人生選択を可能にします。これこそASOVIVAの存在意義なのではないでしょうか。
最後に、今回の講演を聞いて私が感じたことを紹介します。それは、学校のやり方や大勢の中に染まっている自分に対して疑問を持つことは成長への第一歩だということです。疑問を持つことが、これから自分の人生で何をしたいのかを考える原動力になっていると感じました。自分で自分の人生を決めるという価値観を育てることは意義深いことで、周囲とは違った独自の人生選択ができるようになると思います。これが社会にもっと受け入れられれば、多くの人が自分の生き方にゆとりが持てるようになるのではないでしょうか。私には、長村さんの「人生は螺旋状に成長していて、上に向かって成長している」という考え方がとても印象的でした。最短ルートを通らなくても、疑問に思って考えて自分なりの答えを見つけ出す複雑なプロセスこそが「学び」であるということだと思います。普段忙しなく生きていると最短ルートを通ろうとして疑問を持つこと自体忘れてしまいがちです。それでも立ち止まって疑問を持って視野を広げてみたら、小さな学びも見つけることができるかもしれません。大人であろうと子どもであろうと、余裕を持って生きることの大切さは変わらないのです。こうして、身の回りにある環境に感謝したり、そこに落ちている学び、小さな喜びに気づいたりできることで自分の人生は「学び」を通して一層豊かになっていくのだと思います。
国際関係学科1年 さくら
コメントシートより
- 今回の講義を聞いて、学びの形は、ただ学校に通って周りの子供と同じように勉強することだけに限らず、縛られない環境でいろいろな刺激を得ながら多岐にわたる思考をめぐらせていくということも、学びの形なのだということを学んだ。やはり、学びというのは自分の意欲がないと続けられないものであるため、各々が考えた多様なカタチの学びを深めていくためには、周りにとらわれることなく学ぶことができるような、自分に合った環境を選ぶことが大事なのだと改めて感じた。
- 自分と年齢が近いため、同世代の方のお話だと、自然と内容が入ってきた。何が正解なのかわからない、学校に行けないという経験から答えを見つけているのだと感じた。心のコップが溢れたという表現はとてもわかりやすかった。実際に自分も学校と私生活の両立でキャパオーバーしそうになったことが多々ある。その時に支えてくれていたのは同じような境遇にいる友人であったりするため、共感してもらうことや肯定してもらうことが心のコップを溢れさせないコツなのではないかと考える。





