第3回 学生スタッフレポート
手話を始めなければ知らなかったこと〜大学時代の偶然が、いまの仕事に〜
渡邊 早苗 氏(東京聴覚障害者福祉事業協会 東京手話通訳等派遣センター 管理部門長)
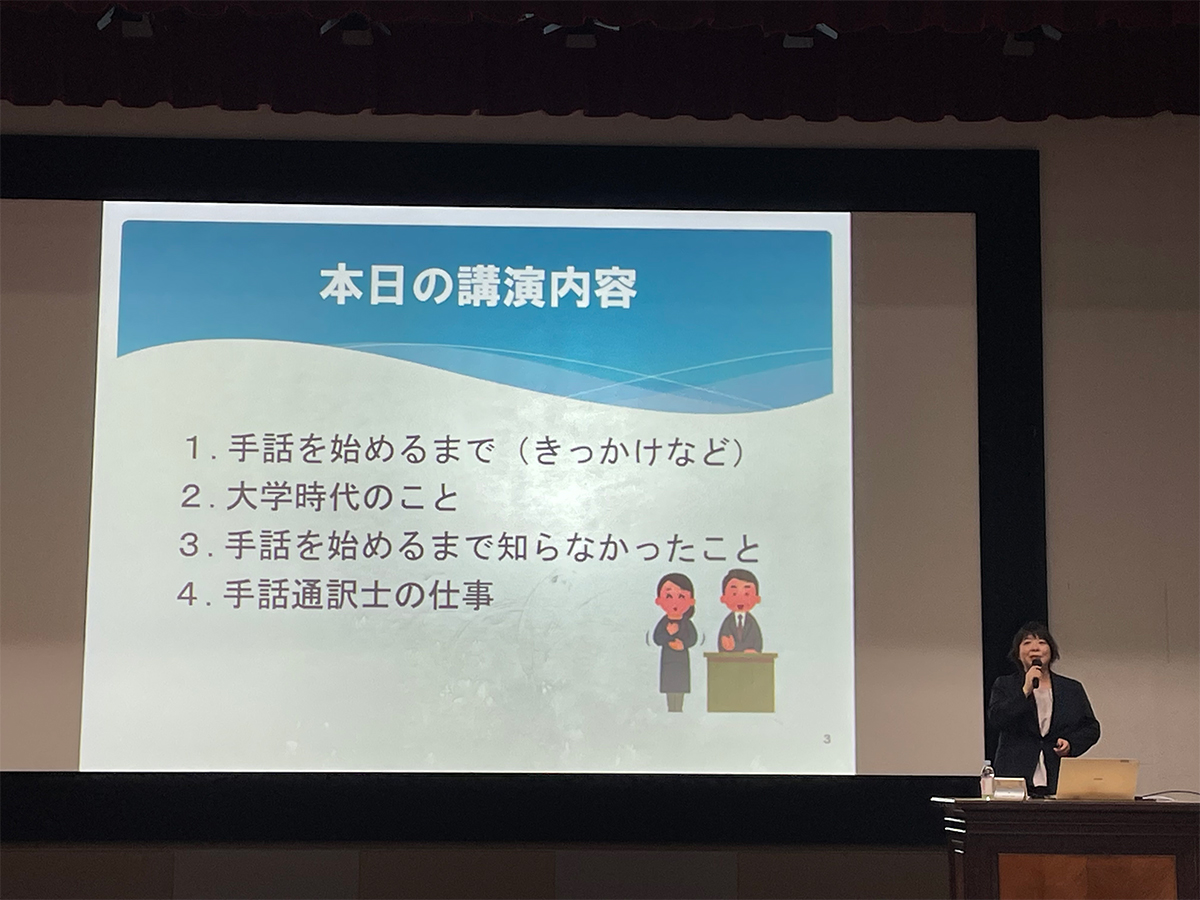
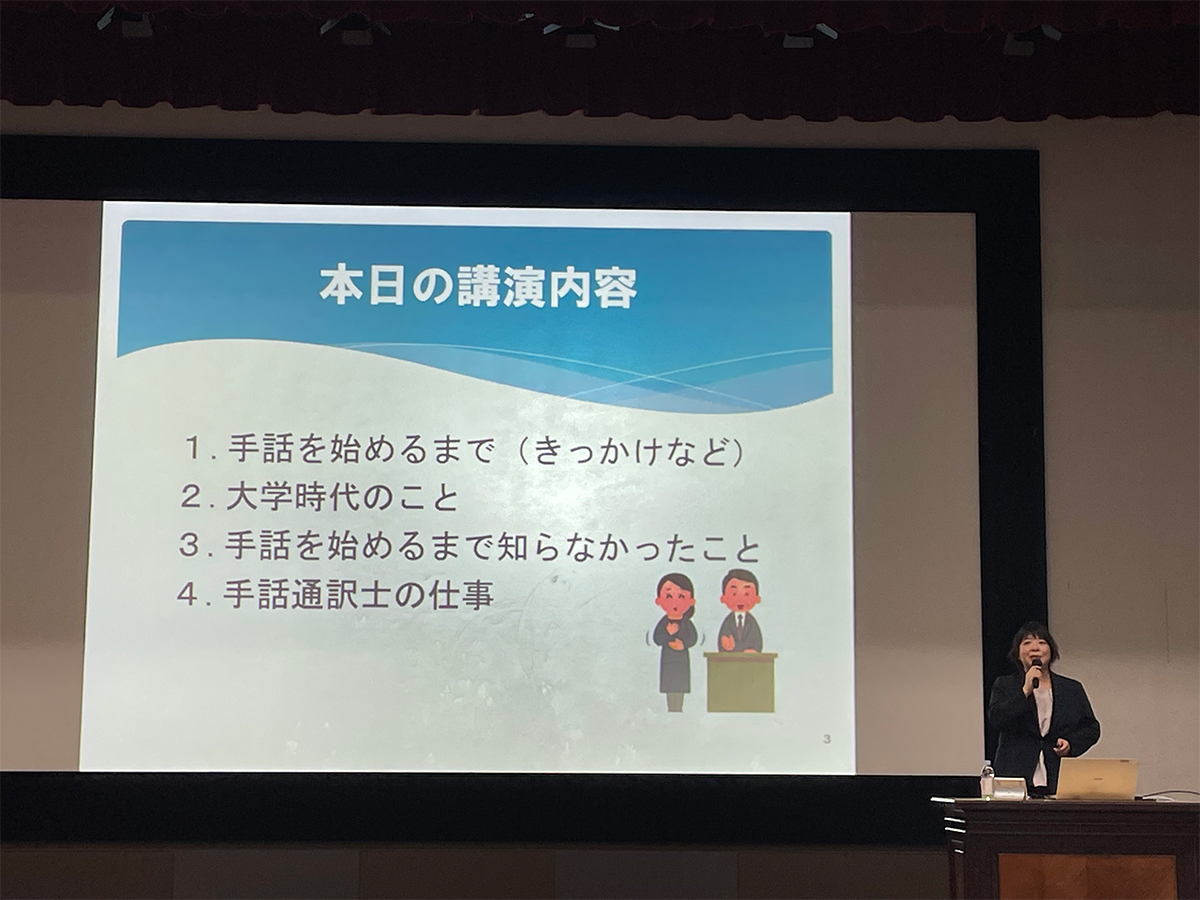
こんにちは!
「総合2024」第3回、5月2日(木)の講演は、手話通訳士として活動されている渡邊早苗さんにお越しいただき、「手話を始めなければ知らなかったこと〜大学時代の偶然が今の仕事に〜」というテーマでお話いただきました。
今回の講演で渡邊さんは、ご自身の人生について、そして渡邊さんが手話を通してどのような影響を受け変化してきたのかという二つの観点からお話しされました。
初めに、渡邊さんの人生と手話との関わりについてお話しされました。渡邊さんの手話との初めての出会いは、中学2年生で参加したキャンプで手話の歌を歌ったことでした。その時に手話を覚えたら楽しそうだと思い、手話に興味を持ち始めたそうです。大学生時代に実際に手話を学び始め、大学の授業やバイトに勤しみながら、手話サークルに通っていたといいます。渡邊さんは現在、東京手話通訳派遣センターに勤めていらっしゃいます。「手話通訳士」という仕事柄、渡邊さんは多くの聴覚障害者の方と出会われてきました。私は今まで聴覚障害を持つ方とほとんど関わったことがなかったため、お話を聞いて、多くの衝撃を受けました。
まず、渡邊さんは、ろう者が社会の中でどのように扱われてきたのかの歴史についてお話しされました。現在、ろう者のほとんどは手話で会話をされています。ですが、ひと昔前までろう学校では「口話教育」が中心で、手話は禁止になっていたといいます。社会に出てから周りの人と対等に会話できるよう、口話教育に力を入れていたそうです。今は手話が身近になり、ろう者もそうでない人も手話を学ぶ機会があるため、当時厳しく禁止されていたということはとても意外でした。
また、「もし自分がろう者だったら」と仮定し、普段何気なく過ごしている日々が、音が聞こえない世界になったら、どのように感じるのだろうということについて、渡邊さんのお話を通して考えました。バスや電車でのアナウンスは日常的に耳にするものだと思います。ですが、 もしバスの停車案内が聞こえなかったり、もし電車が止まった時に理由の説明が聞こえなかったりしたら、目的地までたどり着くのにとても不安を抱えてしまうでしょう。このお話を聞いて、私たちは想像以上に「音」で必要な情報を受け取っているのだと気づきました。また、音で得られる情報には様々あり、話し手の声を聞くことでその人の性別や人柄、感情まで読み取っているのだということも知りました。
皆さんの中には聴覚障害者と出会ったことがないと感じる方も多いでしょう。しかしながら、実は私たちの身近なところに聴覚障害を持つ方がいるのかもしれません。話しかけても反応がなくキョトンとしていたり、異様に大きな声で話したりしている人は聴覚障害を持っている可能性があるそうです。このように、音が聞こえない世界や聴覚障害者についての学びを深めると、日常の風景の見え方も変わってくるかもしれません。
今回の渡邊さんの講演を通じ、相手をよく知り理解することで、より広い眼で世界を見るということの重要性を学びました。私は、今までろう者が多くの苦労をしていることを全く知らずに過ごしてきたのだということに衝撃を受けると同時に、少しずつでも相手を知るということの大切さを実感しました。日常の中で、話している相手や周りの人が「ろう者かもしれない」と想像する力を持ち、相手がどのようなことに苦労しているのかを知ることは、自分の社会に対する見方や向き合い方、人との接し方に変化をもたらすのではないかと思います。そして、このように自分自身が認識していなかった部分が見えることで自分の価値観が変わる、というその変化こそが学びなのではないかと考えました。
また、聴覚障害を持たない渡邊さんが些細なきっかけから多くの努力を重ね、手話の世界に入り活躍されていることを知って、何気ない出来事がその後の人生を大きく変えることもあるのだと学びました。
今回の講義のように手話について学ぶ機会が増えれば、ろう者に対し理解を深め想像力を持って接することのできる人が増えていくでしょう。そして、それが障害のあるなしに関わらず心地よい社会を築くための力になるのではないかと考えます。
「総合2024」第3回、5月2日(木)の講演は、手話通訳士として活動されている渡邊早苗さんにお越しいただき、「手話を始めなければ知らなかったこと〜大学時代の偶然が今の仕事に〜」というテーマでお話いただきました。
今回の講演で渡邊さんは、ご自身の人生について、そして渡邊さんが手話を通してどのような影響を受け変化してきたのかという二つの観点からお話しされました。
初めに、渡邊さんの人生と手話との関わりについてお話しされました。渡邊さんの手話との初めての出会いは、中学2年生で参加したキャンプで手話の歌を歌ったことでした。その時に手話を覚えたら楽しそうだと思い、手話に興味を持ち始めたそうです。大学生時代に実際に手話を学び始め、大学の授業やバイトに勤しみながら、手話サークルに通っていたといいます。渡邊さんは現在、東京手話通訳派遣センターに勤めていらっしゃいます。「手話通訳士」という仕事柄、渡邊さんは多くの聴覚障害者の方と出会われてきました。私は今まで聴覚障害を持つ方とほとんど関わったことがなかったため、お話を聞いて、多くの衝撃を受けました。
まず、渡邊さんは、ろう者が社会の中でどのように扱われてきたのかの歴史についてお話しされました。現在、ろう者のほとんどは手話で会話をされています。ですが、ひと昔前までろう学校では「口話教育」が中心で、手話は禁止になっていたといいます。社会に出てから周りの人と対等に会話できるよう、口話教育に力を入れていたそうです。今は手話が身近になり、ろう者もそうでない人も手話を学ぶ機会があるため、当時厳しく禁止されていたということはとても意外でした。
また、「もし自分がろう者だったら」と仮定し、普段何気なく過ごしている日々が、音が聞こえない世界になったら、どのように感じるのだろうということについて、渡邊さんのお話を通して考えました。バスや電車でのアナウンスは日常的に耳にするものだと思います。ですが、 もしバスの停車案内が聞こえなかったり、もし電車が止まった時に理由の説明が聞こえなかったりしたら、目的地までたどり着くのにとても不安を抱えてしまうでしょう。このお話を聞いて、私たちは想像以上に「音」で必要な情報を受け取っているのだと気づきました。また、音で得られる情報には様々あり、話し手の声を聞くことでその人の性別や人柄、感情まで読み取っているのだということも知りました。
皆さんの中には聴覚障害者と出会ったことがないと感じる方も多いでしょう。しかしながら、実は私たちの身近なところに聴覚障害を持つ方がいるのかもしれません。話しかけても反応がなくキョトンとしていたり、異様に大きな声で話したりしている人は聴覚障害を持っている可能性があるそうです。このように、音が聞こえない世界や聴覚障害者についての学びを深めると、日常の風景の見え方も変わってくるかもしれません。
今回の渡邊さんの講演を通じ、相手をよく知り理解することで、より広い眼で世界を見るということの重要性を学びました。私は、今までろう者が多くの苦労をしていることを全く知らずに過ごしてきたのだということに衝撃を受けると同時に、少しずつでも相手を知るということの大切さを実感しました。日常の中で、話している相手や周りの人が「ろう者かもしれない」と想像する力を持ち、相手がどのようなことに苦労しているのかを知ることは、自分の社会に対する見方や向き合い方、人との接し方に変化をもたらすのではないかと思います。そして、このように自分自身が認識していなかった部分が見えることで自分の価値観が変わる、というその変化こそが学びなのではないかと考えました。
また、聴覚障害を持たない渡邊さんが些細なきっかけから多くの努力を重ね、手話の世界に入り活躍されていることを知って、何気ない出来事がその後の人生を大きく変えることもあるのだと学びました。
今回の講義のように手話について学ぶ機会が増えれば、ろう者に対し理解を深め想像力を持って接することのできる人が増えていくでしょう。そして、それが障害のあるなしに関わらず心地よい社会を築くための力になるのではないかと考えます。
国際関係学科2年 ヒイラギ
コメントシートより
- 話を聞いて自分の視野が広がったような気がします。日常のあらゆる音が聞こえないというのは本当に考えられないことであり、大変な苦労があるだろうと思います。この機会を通してぜひ手話を学んでみたいと思いました。
- 手話をやっていることで、きこえない人の気持ちに寄り添えることは大変すばらしいと思った。日常生活には音があふれており、その一部は文字として伝わっても、すべての情報をきこえない人に届けることはできていないことが分かった。今回の講演で手話の魅力、きこえない人の気持ちを学ぶことができた。
- 大学以外でも学ぶことがいかに有意義であるか、そして、何事にも挑戦し、いろいろな方と接することの重要性を学びました。また、ろう者の体験談から対話やコミュニケーション、相互理解の大切さを痛感しました。





