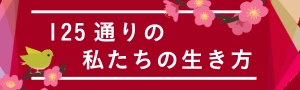第19回 学生スタッフレポート
外国語で読むこと、読まれること
平野 啓一郎 氏(芥川賞作家)
鴻巣 友季子 氏(翻訳家・文芸評論家)


こんにちは、すっかり秋が深まりとうとう冬の足音が聞こえてきましたね。本館の正面にあるクリスマスツリーも点灯し、暗闇に煌々と光る赤や緑がとても幻想的です。こんな季節は温かい布団でぬくぬくと読書に勤しみたい私にとって、この講演はとても興味深いものとなりました。今回の講師は平野啓一郎さんと鴻巣友季子先生です。
平野さんは弱冠20歳、デビュー作『日蝕』で芥川賞を受賞。その後、『マチネの終わりに』は純文学としては異例の17万部を突破し、一躍その名前を知らしめました。さらに今回は翻訳家であり本学で教鞭も取っていらっしゃる鴻巣先生もお招きし、対談形式で講演をしていただきました。今回のテーマは『外国語で読むこと、読まれること』。イチから作品を作り出す文筆家の平野さんと、翻訳を通し既存の作品にエッセンスを加えていく鴻巣先生、似て非なるお二人の対談は一体どんなものになったのでしょうか。
講演担当者の紹介を受け、少し緊張した面持ちで平野さんが登場しました。芥川賞作家というと威厳に溢れた方を想像してましたが、予想に反して物腰柔らかな方でちょっと驚きでした。和やかに話が進む中で津田塾生に最も反響が大きかったのが、デビュー作『日蝕』に関し出版社に送った手紙の話です。平野さんは『日蝕』の出版を新潮社に持ちかける際、編集者の方にある工夫をして手紙を書きました。その手紙は、自分の作品をただ伝えるのではなく「どうしても読みたい、読むなと言われても読みたい」と思わせることを意識して書いたものでした。また、平野さんは、自身のホームページを通して新人作家の原稿が送られてきてもほとんど読んでないそうです。それは、読みたいと思わないから、という至極単純な理由でした。そして多くの人は人に読ませようとしていないというのです。
皆さんは今まで人に読ませようと文章を書いたことがあるでしょうか? 大学生が文章を書くと言ったらレポートくらいで「書きたいこと、書かなきゃいけないことを書く」という場合がほとんどだと思います。さらにそこには“自分”しか登場せず、読み手の顔を想像しながら文章を推敲していく人は稀でしょう。しかし、今後社会に出ると数あるうちから自分を“選んでもらう”という状況が出てきます。さらに、その糸口が手紙やメールであったりして、気の利いた文章ないし一言というのが今後の明暗を分ける、そんなこともあると思います。日頃、文章を読み読まれることを仕事としている平野さんだからこその話を聞けました。私も数あるスタッフレポートから目を止めていただけるよう、皆さんの顔を思い浮かべつつ筆を執っている所存です。
さらに話は『外国語で読むこと、読まれること』に移りました。普段、私たちにとって大学の授業以外では外国語で読む、ましてや読まれるというのはなかなか馴染みのないことだと思います。しかし、外国語で書かれた文章にしかない良さがありました。平野さんは英語とフランス語も堪能で、外国の文学は原書で読むことにこだわりを持っているそうです。また、鴻巣先生は『風と共に去りぬ』の著者である、マーガレット・ミッチェルの訳版を読んだとき「原書では聞こえていたミッチェルの声が聞こえなくなった」と言います。一流の翻訳家が訳した文章なのに、どうして訳語のものではなく、外国語で読むことが大事なのでしょうか?そこには日本語と外国語のどうしても埋められない溝があるようです。例えば英語だと一文一文が日本語より短く、主語と述語はわかりやすく最初に登場します。逆に日本語は句読点で繋ぎ、できるだけ一文を長くする傾向にあり、述語は文の一番後に出てきます。そのような違いがあるため、翻訳を通すとその作者特有の文章の筆致やリズム感が消え、どうしても原書本来の良さが伝わりにくくなってしまうそうです。私は今まで原書を読むのは億劫に感じ、外国作品は翻訳されたものを選びがちでした。しかし、どうも原書にしかない“味”があるようです。その妙味に触れることで新しい発見や作品の楽しみ方に出会えそうですね。
今回の講演を聞いて、私も外国語で読むことに挑戦したくなりました。え?やっぱり外国語で本を読むのは疲れるって?そんなときはこたつに潜ってミカンをお供に本を読んでみてはいかがでしょうか。本を片手に“寝落ち”するのもまた一興です。
国際関係学科2年 ごてんちゃん
コメントシートより
- 鴻巣先生の「何かしなくちゃと思って読むのはつまらない。つまらないから血肉にならない。」というお話を聞いて、大学時代にとりとめもなく本を読みたいと思った。
- 人に自分の気持ちを伝えるのは難しいと思った。私自身、人の気持ちを表現するのが苦手で、そういうことができるようになりたい。