語学、マネジメント、ITを身につけることで グローバル社会の課題を解決できる人材に
安江 令子 YASUE Reiko
学芸学部数学科 1991年卒業
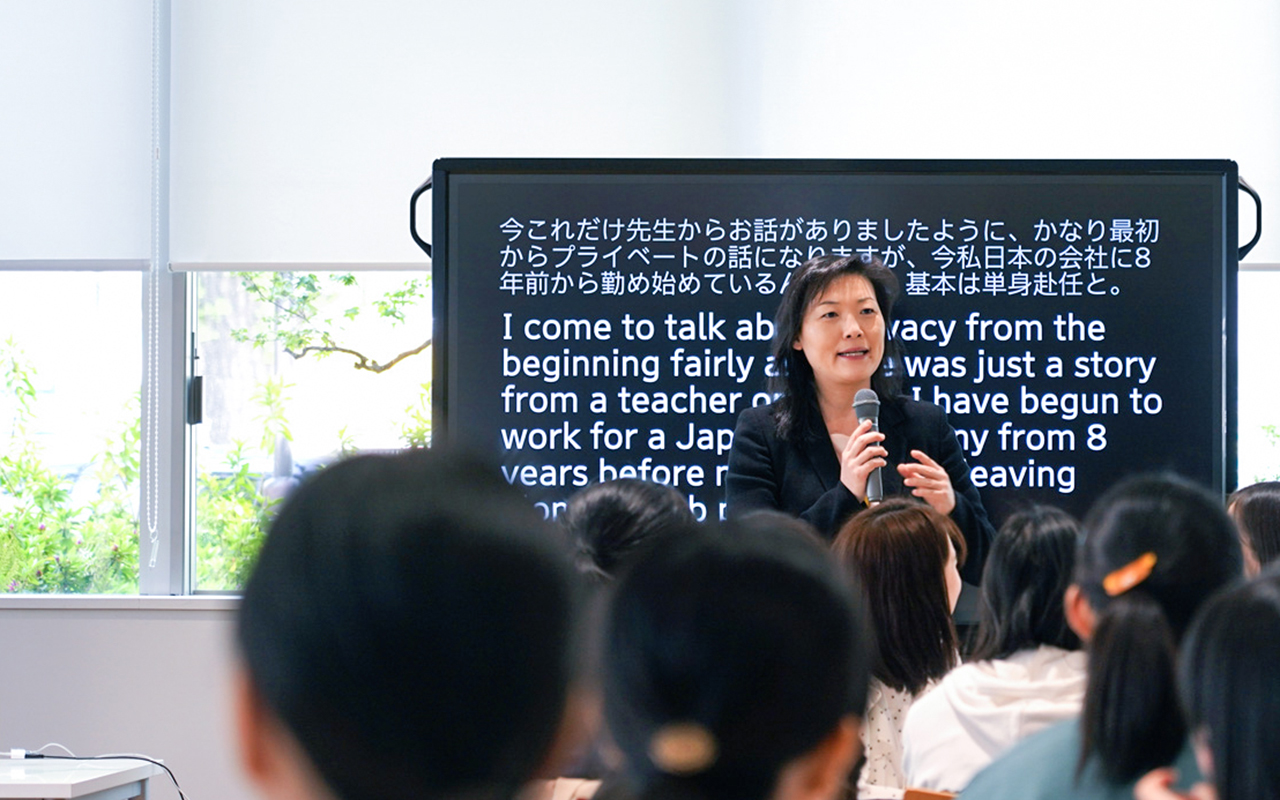
活躍の場を求めて渡米、その経験を伝えるため帰国
私は津田塾大学の学芸学部数学科を卒業し、日本の大手家電メーカーの研究所に就職しました。今から約30年前のことです。当時はまだ「リケジョ」という言葉もなく、技術系の女性が非常に少なかった時代でした。数少ない一人の先輩女性研究員の方から、「女性は男性の二倍働いたって、一緒にはならないわよ」と言われたことを、今でも覚えています。この方は結婚をされていて、子どもを預けながら朝7時に出社され、早めに退社されていました。私はそんな彼女を見ながら、「仕事がやりにくいな」と思うばかりで、「出張に行く際には、お子さんをどこへ預けるんだろう」などと考えることは全くありませんでした。後に自分が同じような境遇に陥るとは、予想だにしていませんでした。当時の私は女性が働くことに対する意識や思いやりに関して、周囲の男性社員並みどころか、誰よりも低かったのではないかと思います。
そうした中、私はエンジニアとして通信方式の標準化活動に日々取り組んでいました。私が社会に出た1990年代前半は、まだインターネットが世の中に普及していなかった時代です。携帯電話に関しても、現在の基礎となる「無線でインターネットを行う技術」が国際標準となる時期で、私もその技術を自分の会社に取り入れようと仕事に燃えていました。そのために世界中のカンファレンスに参加し、プレゼンテーションを繰り返していたのです。数学科出身ですので皆さんのように英語を身につけておらず、海外でのプレゼンテーションではかなり苦労しました。ただ、エンジニアの場合は状態遷移図という設計図のようなものを通して、お互いの意図を理解できるんですね。そうやって国際カンファレンスなどを通して経験を積み、英語についても徐々に身につけていきました。


けれども当時の日本企業は男性中心の社会です。そうしたことでの苦労も味わい、より活躍できる場を求めて、アメリカのIT企業への転職を決意したのです。 そしてシリコンバレーでエンジニアとして働き始めたわけですが、今思い出してみても天才ばかりが集まった環境でした。私がどれだけ探しても見つけられないシステムのバグを、一瞬で見つけられるエンジニアたちに囲まれ「自分はここでエンジニアとして食べていくことなんて、到底できないかもしれない」と思いながらも働かなければいけませんから、彼らと一緒に懸命に働きました。海外へと飛び出して、そんな優れた才能と接したことは私にとって非常によい経験になりました。そうやって転職もしつつ、キャリアを重ねました。電子・通信機器の会社でも働きましたし、半導体を製造している会社でも働きました。多分皆さんのスマートフォンに使われている半導体は、ほぼ当時私が働いた半導体企業で作られたものです。現在同社は世界屈指のメーカーとなりましたが、私が入社したのはその直前の時期で、だからこそ会社がドラスティックに成長していく過程を見ることができましたし、私自身も多くの経験を得ることができたのだと思っています。
そのように米国で働きながらも、私は日本の動向にも注視していました。当時の日本はまだ景気も良く、10社を越えるメーカーが、フリップフォンと呼ばれる折りたたみ式の携帯電話を毎シーズン競うように発売していました。皆さん、ガラパゴスって聞いたことがありますか? 限られた場所での既得権益を守ることに固執して、結果的には時代に取り残されてしまうことを指します。その代表的な事例が日本の携帯電話で、ガラパゴスケータイ、ガラケーという言い方をしますよね。当時は台湾、韓国、そして中国から、通信機器の新しい国際標準ともいえるスマートフォンが続々と発売されて、あっという間に日本勢は全滅してしまいました。現在でもスマートフォンを製造し続けている日本メーカーは、数える程度しかないですよね。時代の大きな流れに飲み込まれていく日本企業の様子を、遠く6,000マイル離れた海の向こうで見ているしかなかった私は、「すごいことが起こっているな」と感じていました。一体、日本企業は、そして日本のものづくりは、これからどこへ向かうのだろう。当時の私はアメリカで転職を重ねた結果、非常にいいポジションをいただいて、充実した毎日を過ごしていました。けれどもそういった状況を見て、「もう一度、日本に戻ってみよう」と思い立ったのです。自分の海外での経験を持ち帰り、日本のグローバル化に少しでも貢献できたなら、人生を振り返ったときに良かったと思える日が来るのではないか。そう思い、10年前に日本の会社へ転職しました。津田塾大学を卒業してから、約20年の月日が経っていました。
AIが台頭する時代だからこそ、求められる人に
日本に帰国後も一度転職し、そのグループ会社である現在のサイバネットシステムで働き始めたのが昨年のことです。サイバネットシステムはITソリューションなどを取り扱う会社ですが、先日AIを使用した医療用の大腸内視鏡ソフトを開発し、日本で初めてAIを持った医療用ソフトウェアとして販売の許可を受けました。内視鏡によって撮影された大腸の画像をAIが解析し、ポリープの腫瘍/非腫瘍をAIが判断するもので、一般の病院でも使用されはじめています。
少し話が飛びますが、最近、GAFAというフレーズをよく耳にされると思います。IT系の大企業の頭文字を取ったフレーズですが、これからの社会ではこのGAFAがAIを使って、これまで人間が行ってきた多くの仕事を行うだろうといわれています。便利になる一方で、多くの仕事はAIに奪われてしまう。そんな時代が間もなくやってくるのです。けれどもいくつかの職種については、これからも人間が引き続き行う必要があるともいわれています。私たちの会社はAIによる大腸内視鏡ソフトを開発しましたが、AIに「アナタハ大腸がんノstage 4デス」と言われるよりも、やはりお医者さんに言われたほうがいいですよね。また弁護士の仕事も、判例についてはAIが行うことになると思いますが、込み入った話になると弁護士が担当するのではないでしょうか。そうした信用に関わる仕事や、カウンセラーやセラピストといった人間のメンタルに関わる仕事、さらにクリエイティビティが求められる仕事などは、これからも人間が行っていくと思います。ただ、「ガウディのような建造物を設計してほしい」とAIに言ったら、本当に作ってしまう時代が来るかもしれないですよね。


MBAを彷彿とさせる、総合政策学部のカリキュラム


- 主催:
- 津田塾大学総合政策学部
- 共催:
- 平成30年度文部科学省 私立大学研究ブランディング事業
「『変革を担う女性』の持続的育成を目指した『インクルーシブ・リーダーシップ研究』拠点の形成」
1991年学芸学部数学科卒業。同年大手家電メーカーの情報システム研究所に就職。1999年に渡米しエンジニアとして数多くの企業で活躍。2009年に帰国し、富士ソフト株式会社に就職。同社執行役員などを経て、2018年にグループ会社であるサイバネットシステム株式会社の副社長執行役員、2019年に同社代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)に就任。
サイバネットシステム株式会社ウェブページ





