田邉 恵子 准教授
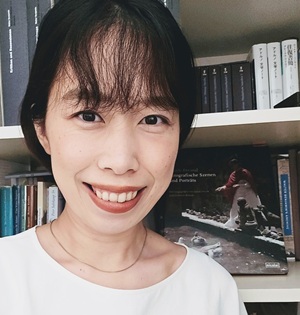
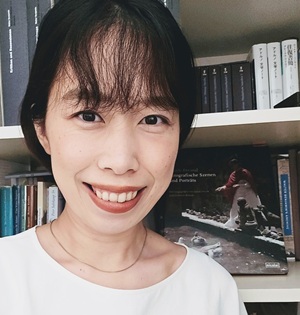
高校生へのメッセージ
「思考の声なき対話は自己と自己自身とのあいだに行われる」——思想家ハンナ・アーレントはこう書いています。内なる対話は、それまで知らなかった自己との出会いをもたらし、新たな目で世界を見るための力になります。
同時に、書物のなかに生きる過去の人たちとも対話してみましょう。テクストに書き込まれた他者の声=言葉を聴くことで、自分の内なる声もまた引き出されることになるでしょう。あなた自身の生を導いてくれる言葉に出会う、そんな時間を過ごしてみませんか。
同時に、書物のなかに生きる過去の人たちとも対話してみましょう。テクストに書き込まれた他者の声=言葉を聴くことで、自分の内なる声もまた引き出されることになるでしょう。あなた自身の生を導いてくれる言葉に出会う、そんな時間を過ごしてみませんか。
私の研究
戦間期ドイツの思想や文学、とくに、ユダヤ系文筆家ヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)のテクストが専門です。彼が亡命期に執筆した回想録『1900年ごろのベルリンの幼年時代』(1938)を読解する作業に長く取り組んできました。研究の手法としては、テクスト生成論/文献学的読解と言えると思います。完成原稿だけではなく、習作やノートといった関連資料、さらには削除線が引かれている箇所も読み解くことによって、ベンヤミンの思惑に可能な限り近づくことを目指しています。日本語で紹介されていない資料を論文で取り上げたり翻訳したりするのが大きなやりがいです。
ベンヤミン研究から派生して、ひとにとっての「幼年時代」「故郷」「家」とはなにか、という問いにも取り組んでいます。この問題系においてはテオドール・アドルノ、マルティン・ハイデガー、オットー・フリードリヒ・ボルノウといったドイツ語圏の思想家たちはもちろん、ジョルジオ・アガンベンやエマヌエーレ・コッチャの言説にも注目しています。
また、最近では書物論の勉強もはじめました。とくに装丁家の言葉や実践に着目しています。擦り切れたり、折れ曲がったりするからこそ愛おしい一冊——液晶画面上で見る文字情報とは異なる、手触りのある書物(ときにそれは人間の脆い身体にも似ています)の可能性についていろいろと考えているところです。







