籠 碧 講師
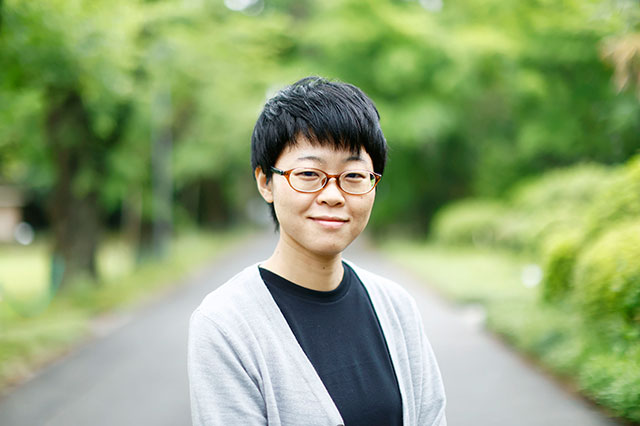
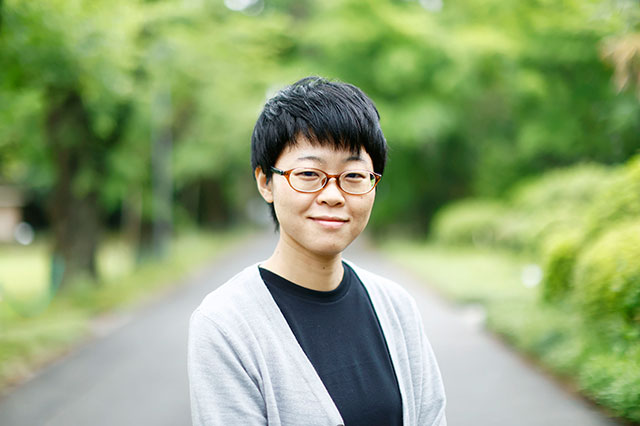
高校生へのメッセージ
「生きづらさ」の感覚が問題意識に結びつくことは多々ありますが、この結びつきをフルに活かせるのが大学という場だと思います。高校生のいま違和感を覚えることが多ければ多いほど、国際関係学科での時間は(派手ではなくとも)濃密なものになるはずです。自信を持って勉強してください。
私の研究
「マイノリティには特殊な才能がある」という物言いを近年よく耳にしますが、そうした言説の直接の源流の一つに実は20世紀初頭のドイツ語圏の文学があります。モダニズムと呼ばれるこの時代、医学が整備されるに伴い文学の中に狂気のイメージが氾濫しました。とりわけ目立ったのが、精神の病や障害を持つ人々をラディカルに称揚し、天才や神として描き出した表現主義の一派です。冒頭の言説が今の私達にときに暴力的に響くのは、「才能がないマイノリティは排除してよい」という前提を暗に含んでいるからです。そして事実そのような主張はモダニズム期からすでにあり、ナチス・ドイツの暴力に加担したとすら言えます。私はこれまで、才能を軸にマイノリティをジャッジする言説を批判的に眺めるとともに、一義的な称揚イメージに回収されないモダニズム期の狂気イメージを取り出す研究を行ってきました。革新をこととするモダニズムの時代にあってはむしろ保守的と評価されることの多い作家——たとえばシュニッツラーやシュテファン・ツヴァイク——の狂気イメージに注目し、それらを仔細に眺めてみれば、医学への懐疑的なまなざし、健常と異常を逆転的にとらえる見方、あらゆる人を病とみなす世界観など、実に多様で柔軟な考えが息づいているのがわかります。紋切り型を離れたイメージにこそ、文学の底力を感じ取ることができるのです。今後はさらに幅広く、「囲い込まれた存在」としてのマイノリティがどのように表象され、そしてその表象が社会にどのような影響を及ぼすのか、考察したいと思っています。
私自身がマイノリティと才能を結びつける言説のために「何かに秀でていなければ受け入れてもらえない」という思いに長い間苦しめられました。そうした言説に救われる局面もあるにせよ、私には一貫して暴力でした。学問の醍醐味の一つは思い込みの呪縛を解き放つ力にあり、しかもそのきっかけは往々にして意外な場所に落ちています。学問の世界は広大ですから、みなさんもきっとご自身の文脈でその醍醐味を実感できるはずです。
私自身がマイノリティと才能を結びつける言説のために「何かに秀でていなければ受け入れてもらえない」という思いに長い間苦しめられました。そうした言説に救われる局面もあるにせよ、私には一貫して暴力でした。学問の醍醐味の一つは思い込みの呪縛を解き放つ力にあり、しかもそのきっかけは往々にして意外な場所に落ちています。学問の世界は広大ですから、みなさんもきっとご自身の文脈でその醍醐味を実感できるはずです。




